「与える」「受け取る」「返す」──この三つの動作だけで、社会が秩序を持つとしたら?
国家も法律も暴力も存在しない世界で、人びとはどうやって関係を築いてきたのか。
フランスの人類学者マルセル・モースは、答えを「贈与(ギフト)」の中に見いだした。
本記事では『贈与論』を手がかりに、国家が現れる以前の“交換による秩序”を掘り下げ、
グレーバーのアナーキズム的視点とも重ねながら、宗教と社会をつなぐ“贈ること”の力を見直していく。
贈与は“取引”ではない
「贈与」とは何か。
辞書を引けば、「好意によって物を無償で与えること」とある。
だが、無償で与えたはずのものに、「返さないといけない」というプレッシャーを感じた経験がないだろうか?
出産祝いに内祝い、職場の差し入れへのお返し、お歳暮──日本社会にも贈与は満ちている。
そして、その多くに「形式的なお返し」が暗黙のうちに期待されている。
それはなぜなのか。
マルセル・モースの『贈与論』(1925年)は、この問いに人類学的に答えようとした古典的名著である。
彼が見たのは、国家も貨幣も契約書も存在しない先住民社会において、贈り物のやりとりがどのように社会の秩序を支えていたかという事実だった。
与え、受け取り、返す──この循環が秩序をつくる
モースが着目したのは、贈与が三つの義務によって成立しているという構造だ。
- 与える義務(give)
- 受け取る義務(receive)
- 返礼する義務(repay)
この3つは、いずれも法律や罰則によって強制されるものではない。
しかし、それを怠れば社会的信用を失い、共同体からの信頼を損なう。
つまり、法によらない秩序がここに存在する。
たとえば、ポリネシアの儀礼的贈与「ポトラッチ」では、部族間の序列や威信が、大量の贈与によって示された。
単なる物の交換ではなく、社会関係そのものを維持・更新する行為だったのだ。
モースはこれを「全体的贈与(total prestation)」と呼んだ。
全体的とは、経済的な意味に限らず、**宗教的・道徳的・政治的意味を含んだ“複合的な義務”**という意味である。

贈与は“経済”ではなく“倫理”
近代資本主義における経済は、「等価交換」を前提とする。
売った側と買った側は、お金という基準で関係を清算する。そこに継続的なつながりは生じにくい。
一方、贈与はあえて等価ではなく、時間差と曖昧さを内包する。
いつ返すのか、何を返すのか、いくら相当か──それらが明確でないからこそ、関係が継続される。
これはまさに、「社会のための不完全な取引」である。
計算され尽くした契約ではなく、返すべき“心”が残るやりとりこそが、人と人を結びつける。
そしてこの「返さねば」という思いは、他人からの命令ではなく、「自分の内側から発生する“道徳的圧力”」である。
ここに秩序が生まれる。
なぜこれが“秩序”なのか?
私たちは秩序を、法律やルールのように“明文化されたもの”だと考えがちだ。
だが、社会を円滑に動かしているものの多くは、実際には「空気」「遠慮」「暗黙の了解」といった非明文化の力だ。
モースの贈与論が示すのは、こうした非明文化の圧力が、国家も法もなくても、人と人のあいだに“義務”を発生させる力を持つということだ。
国家の秩序が“上から”の強制だとすれば、贈与による秩序は“横から”の期待である。
期待されているから返す──そこに恐怖も罰もない。だが、見えない倫理的な回路が機能している。
つまり、贈与とは単なる「与えること」ではなく、秩序を流通させる技法だったのだ。

贈与は“社会を結ぶ契約”だった
マルセル・モースは、贈与には「与える・受け取る・返す」という3つの義務があると述べた。
これらは法や契約に基づくものではないが、履行されなければ社会的信用を失う。
つまり、贈与は「物のやりとりを超えて、関係の継続を前提とした“非明文化の契約”」として機能していた。
宗教と儀礼が秩序を媒介する
贈与が単なる「物のやりとり」ではないことは、すでに見てきた。
では、なぜそこまで重みのある行為になりえたのか。
なぜ、ただ“モノをあげる”というだけのことに、道徳や義務、さらには恐れさえ伴ったのか。
マルセル・モースが特に重視したのが、贈与に内在する宗教的要素だった。
見えない力──マナ、霊、祖霊
モースが分析したポリネシアやメラネシアの社会では、「贈り物」とされる物には、マナ(霊的な力)が宿ると信じられていた。
つまり、贈与とは単なる行為ではなく、「魂の一部を渡すこと」でもあった。
この考え方は、『贈与論』の中でもたびたび現れる。
「モノには贈り主の霊が宿っている」
「贈り物を返さないことは、霊の力を腐らせることになる」
「神に捧げられた供物を受け取るのは、神との契約に入ることだ」
これらの例に共通するのは、「物を通じて関係が形成され、それが社会秩序に不可欠だった」という点だ。
つまり、宗教や儀式は、贈与の背景として“見えない力の存在”を保証し、行為に意味と重みを与える役割を担っていた。
国家の前に、神が秩序を保証していた
現代では、義務や責任の多くは法律によって規定される。
しかし国家のない社会では、秩序を支えるものは**人間の内面にある“恐れ”や“敬意”**だった。
たとえば、祖先の霊に怒られることを恐れて返礼を怠らなかったり、
神のタブーに触れることを避けて行動を慎んだりする。
これは、単に「信仰心」の問題ではない。
神や霊の存在が“秩序を監視する目”として働いていたということだ。
ルース・ベネディクトが『菊と刀』で描いたように、
「恥の文化」では他人の目が行動の規範になるが、
それ以前には「神の目」が、人びとの行動を律していた。
言い換えれば、国家による強制力のない社会でも、宗教的な“見えない圧力”が秩序を生んでいたのだ。
儀礼は“関係の更新”の儀式
また、贈与は一度きりの行為ではなく、定期的に繰り返される儀礼の中で交わされていた。
たとえば北西アメリカの先住民社会では、「ポトラッチ」と呼ばれる儀式がある。
これは、贈与によって部族間の威信を競い、かつ関係を更新する重要な社会的イベントだった。
贈与と儀礼は切り離せない。
儀礼とは、モノのやりとりを「ただの交換」ではなく、「社会的関係の再確認」へと変えるための装置だ。
そしてその根底にあるのが、神聖なものへの畏敬、祖先との絆、共同体への帰属といった宗教的感情だった。
結局、何が“秩序”をつくっていたのか?
秩序とは、ルールや契約ではなく、関係と意味づけによって維持されていた。
神の目があり、霊が宿り、儀礼が繰り返される──それが社会の一体感をつくり、
贈与の義務を「やらされること」ではなく「やるべきこと」へと変えていた。
国家なき秩序は、宗教によって支えられていた。
それは暴力や刑罰ではなく、見えない力による内面化された統治だったとも言える。

神がルールを見張っていた時代
国家のない社会では、秩序は法律や警察ではなく、「見えない存在」によって支えられていた。
祖霊信仰、神々、タブー、、、
これらは単なる宗教的迷信ではなく、行動を規制する“社会的な目”として機能しおり、モースは、こうした宗教的世界観が贈与の義務感を強化し、社会の統合をもたらしていたと考えていたんだ。
アナーキズムと贈与の交差点
アナーキズムというと、しばしば「国家を否定し、権力に反抗する思想」として語られる。
けれど、グレーバーが見たアナーキズムは、それだけではない。
むしろ彼が重視したのは、「国家や強制力がなくても、社会は別のかたちで秩序を維持できる」という事実だった。
そしてその“別のかたち”の一つが、モースの描いた贈与のメカニズムである。
支配ではなく、義理と倫理でつながる社会
グレーバーは、人類学者として数多くの非国家的社会を見てきた。
そこでは、警察も裁判もないのに、人びとは争わず、関係性を保ち、時には助け合いながら暮らしていた。
どうしてそれが可能だったのか?
モースが指摘したように、人と人のあいだには「与える・受け取る・返す」という一連の動きがあった。
それは単なる物流ではなく、信頼と互恵の循環であり、社会的な関係を維持する装置だった。
国家が関与せずとも、人は「もらいっぱなしではいけない」と思い、
返すことで関係を継続させる。
そこには、自発的な義務感と倫理的な圧力が機能していた。
これは、まさにアナーキズム的秩序の原型だ。
国家に頼らない関係性のインフラ
贈与による秩序は、現代社会でも意外なかたちで残っている。
たとえば、ボランティア、フリースクール、相互扶助のネットワーク、食料配布イベント、
あるいは「時間銀行」や「地域通貨」など、金銭によらない支え合いの実践がある。
これらは国家の制度に組み込まれていないが、しばしば国家よりも柔軟で、
かつ参加者同士の“信頼”に支えられている。
返礼は法律ではなく、「関係性の中で求められるもの」だ。
グレーバーはこうした実践を、「プレフィギュラティブ・ポリティクス(未来の社会を先取りして生きる政治)」と呼んだ。
つまり、アナーキズムとは「国家の否定」ではなく、
国家を経由せずに、すでに始まっている別の秩序のかたちなのである。
贈与経済は“非効率”か?
もちろん、贈与には効率性はない。
返すべきタイミングも金額も不明確で、損得も不透明だ。
しかしそれでも、贈与の秩序が成立するのは、
人間が“計算”ではなく“関係”を大切にする生き物だからだ。
国家による秩序が罰や強制を必要とするのに対し、
贈与の秩序は、自発的に関係を保とうとする意志に依存している。
ここに、国家なき秩序のリアルな可能性がある。
支配されずに生きるための技法
贈与は、反抗ではない。
破壊でも、革命でもない。
それはただ、「支配されずに生きるための技法」として、
人類の長い歴史のなかで育まれてきた。
そしてそれは今も、私たちのすぐ隣にある。

0円コーヒーも“贈与”の技法?
マクドナルドがかつて行っていた「無料コーヒー」キャンペーンは、単なるサービスではなく、来店者に無償で与えることで、「返さなければ」という心理的圧力(互酬性の期待)を生じさせる構造があった。
これはモースのいう贈与の基本構造(与える・受け取る・返す)に酷似しており、現代のマーケティングにも贈与的秩序の原理が活きている好例だね。
贈与の終わりと資本主義の台頭
贈与には、不思議な力があった。
人と人とをつなぎ、義務を生み、社会を動かしていた。
だが、いつの間にか私たちは、その力を手放してきた。
なぜ贈与は、社会の中心から追いやられたのか?
その問いの先には、資本主義という別の秩序が見えてくる。
贈与が“制度化”されたとき
モースが描いた贈与の世界は、しばしば儀礼や信仰と結びついていた。
それはコミュニティの内部で機能し、関係性を優先したネットワーク型の秩序だった。
しかし国家が発達し、法制度と官僚機構が整うにつれて、贈与は“非効率なもの”と見なされ始める。
行政的には煩雑で、税制にも不向きで、何より「透明性」に欠ける。
そして、国家は贈与の精神を“制度”に変換しようとした。
それが、「福祉」や「公共サービス」といった形での“機械化された贈与”だった。
つまり、“誰から”でもなく、“誰に”でもなく、顔のない与え方。
そこでは、返礼も関係性も、もはや期待されない。
贈与は、制度に吸収された時点で、“関係をつなぐ行為”から、“手続き”になったのだ。
資本主義の秩序とは何か?
その一方で、台頭してきたのが市場による秩序だ。
市場経済では、贈与のような曖昧さは敬遠される。
等価交換が原則であり、感情や関係性ではなく、価格と契約がすべてを決定する。
- 「誰からもらったか」より、「いくらで買ったか」
- 「返さなければ」より、「払ったからそれで終わり」
- 「空気を読む」より、「規約を読む」
この秩序は非常に合理的で、拡張性も高い。
だが、モースが描いたような「贈与によって社会をつなぐ」機能は、そこにはない。
むしろ、人と人を“つながらなくてもいいように”する装置として、資本主義は進化してきたとも言える。
国家と資本の結託
ここで注意すべきは、国家と資本主義がしばしば同じ秩序の側に立っているという点だ。
国家は税制や金融制度を通じて市場経済を支え、
市場は国家の中で活動する企業や個人に、契約的な行動様式を求める。
その結果、社会のあらゆる場面が「取引化」され、
贈与のような“余白”や“曖昧な義務”が排除されていく。
「誰にも強制されてないのに、みんな返してる」
そんな贈与的な社会は、
「強制されなきゃ誰も返さない」社会へと、
静かにすり替えられていった。
贈与は過去の遺物か?
それでも、贈与は完全には消えていない。
お年玉も、手土産も、ふとした差し入れも、
私たちの周囲にはまだ“関係をつなごうとする与え方”が残っている。
だがそれらは、もはや秩序の中心にはいない。
むしろ、「経済の外」「制度の隙間」に追いやられている。
そしてそれは、「非合理」「非効率」として、やがて“自己責任”とぶつかることになる。
贈与的な社会があったことすら、なかったことにされる日が来るかもしれない。

資本主義は“つながらなくても成立する秩序”
贈与経済は関係性の維持を前提とした“顔の見える秩序”だったが、資本主義は価格と契約に基づく“顔の見えない秩序”を好むんだ。
この非人格的な構造が、遠くの他人とも取引を可能にし、社会の拡張を加速させた一方で、義理や恩といった関係性のしがらみを切断していくこととなんたんだ。
秩序を選びなおす──贈与の可能性は終わっていない
モースが描いた贈与社会は、国家も法も通貨もなかった時代の話だ。
そしてその後、国家は力を持ち、市場は拡張し、資本主義が社会を組み直した。
現代において、贈与の秩序は“非効率”のレッテルを貼られ、
制度の外縁で、細々と息をしているようにも見える。
だが、それは本当に“終わった話”なのだろうか?
「役に立たない」が、なぜか続くもの
お中元、お歳暮、差し入れ、手書きの手紙。
返礼の時期を逃し、義務でもないのに、どこかで「返さなきゃ」と思ってしまう。
そこには、合理性や取引の論理では説明できない“空気のような倫理”が残っている。
そして不思議なことに、その空気があるところでは、人と人のつながりが切れにくい。
贈与は非効率だが、関係をつくる。
贈与は曖昧だが、信頼を深める。
贈与は計算されていないが、社会を温める。
この非対称なやりとりは、国家の法ではなく、人間の関係にしか生まれない秩序だ。
プレフィギュレーション──未来を先に生きる
グレーバーが好んで用いた言葉に「プレフィギュラティブ・ポリティクス」がある。
それは「いつか来る理想社会を目指す」のではなく、
その社会を“今この場”で実践することを意味する。
たとえば、互助の仕組み、共育、贈与経済に近い地域通貨、ボランティア、シェア型の暮らし──
すでに始まっているそれらは、国家にも資本にも命じられていない。
でも、そこには“秩序”がある。支配のない秩序、信頼に支えられた秩序だ。
それらは、グレーバーに言わせれば、アナーキズム的秩序の萌芽である。
あなたが守りたい秩序は、誰のためのものか?
社会の秩序は、必ずしも「国家」「法律」「価格」だけでできているわけではない。
モースが描いたように、贈与にも秩序は宿る。
その秩序は、恐れや罰ではなく、信頼と継続の中に生まれる。
もちろん、それは不安定だ。強制力もない。
けれど、それを「理想論」と切り捨てるのは簡単すぎる。
“贈与が秩序をつくる”という思想は、今なお──いや、今だからこそ──見直すに値する。
あなたが信じている秩序は、本当にあなた自身が選んだものだろうか?
それとも、誰かが“あたりまえ”だと言ったものに、ただ従ってきただけだろうか?
今もなお、秩序は選びなおすことができる。
そして贈与は、その選びなおしのきっかけになりうる。

“プレフィギュラティブ・ポリティクス”とは?
「未来の社会を、現在の実践で体現する」という意味。
たとえば、上下関係のない会議運営、貨幣を使わない助け合い、権威に頼らない教育、
それらはすべて、“国家の外”で社会がどう機能するかを、今ここで試すためのプロトタイプといえるね。
シリーズ:アナーキーという秩序
- 「国がなければ無秩序」は嘘?グレーバーが見た“もうひとつの秩序”
- 今読んだ記事→ 交換が社会をつくるモースの『贈与論』が照らす“与えあう秩序”の原型
- 国家は誰のものか?人格化された国家から装置としての国家へ
- 「無政府状態=無防備」なのか?──アナーキズムと“自衛する社会”の可能性

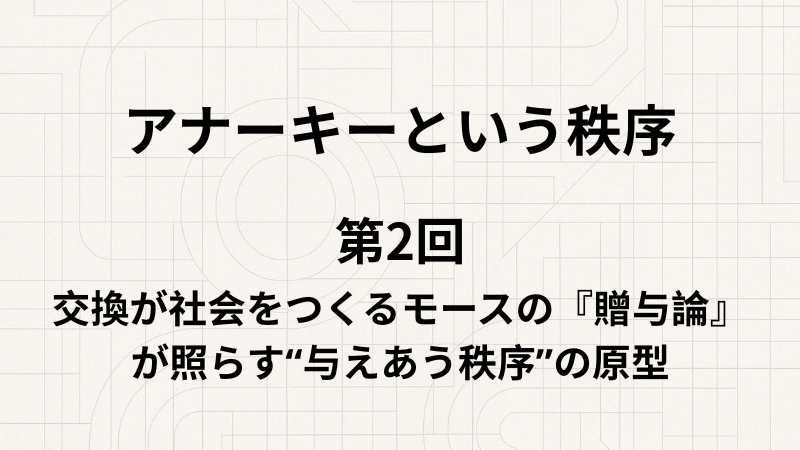
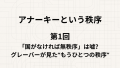
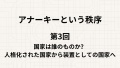
コメント