制度とは、社会の課題に対して合理的な解決を与えるために設計される「仕組み」のはずだ。
しかし時として、制度はその目的を見失い、ただ「守ること自体」が目的となる。
そうなると制度は、もはや制度ではない。信仰である。
「制度の目的喪失」という観点から、いまなお日本社会を二分している「夫婦別姓」問題を見つめ直す。
そこには、形式を守ろうとする力と、柔軟な更新を求める声のぶつかり合いがある。
制度とは何か。そして、制度を守るとはどういうことか。
私たちはいま、その根本を問い直す地点に立っているのではないか。
制度とは、問題を解決するための仕組みであるべき
制度とは、社会に生じる問題を解決するために作られる「道具」である。
人々の安全を守るため、対立を避けるため、秩序を維持するため──そこには必ず目的があるべきだ。
しかし、時代が変わるなかで制度の「理由」が忘れられ、形式だけが残ることがある。
なぜそれが必要なのかと問うても、「昔からそうだから」「それが正しいから」としか返ってこない。
目的が消え、形式だけが独り歩きする。それは制度ではなく、もはや宗教である。
宗教の戒律も、本来は経験則や合理性に基づいたものであった。
ヒンドゥー教の不浄観念、イスラム教のラマダーン、ユダヤ教の食事規定、仏教の五戒──
どれも当初は、衛生、集団秩序、内面の修養といった実践的な意味を持っていた。
だがそれが「神の命令」「伝統」という名で絶対化されると、理由を問うことがタブーとなる。
現代の制度にも、こうした「聖域化」が進んでいる例は少なくない。
夫婦同姓という信仰
日本の制度の中で、もっとも「信仰」に近い性質を帯びているもののひとつが、夫婦同姓制度である。
世界を見れば、結婚によって姓をどう扱うかは本人の自由である国が大半だ。
しかし日本では、結婚するカップルには「同じ姓」を選ぶことが法律で義務づけられている。
これは事実上の姓の統一強制であり、とくに女性に改姓の負担が偏っている現実もある。
かつて、家制度や戸籍の整理においては「夫婦が同姓であること」が意味を持っていた。
だが今、その前提はすでに崩れつつある。
「家」よりも「個人」が尊重され、アイデンティティの継続性が重視される時代において、「同じ姓でなければならない」という根拠は揺らいでいる。
にもかかわらず、それを変えようとすると強い反発が生まれる。
その反発は、しばしば制度の目的とは無関係な「家族らしさ」「絆」「子どものため」といった情緒的な語彙で語られる。
それはつまり、「信仰」に近い。
反対派の論理──「制度の崩壊」がもたらす不都合
もちろん、すべての夫婦同姓賛成論が非合理というわけではない。
制度の整合性を重視する立場からは、一定の理屈に基づいた反対意見も存在する。
たとえば、戸籍制度との整合性を挙げる人がいる。
現在の日本の戸籍は「家単位」で構成されており、夫婦同姓はその単位を明確にする機能を持っている。
別姓を許容することで、制度全体の再設計が必要になる。これはコストや混乱を生む可能性がある。
また、姓の不一致が親子関係に与える影響や、学校・病院などでの対応が煩雑になるという現実的な懸念もある。
子どもの姓をどうするか、社会的にどのように説明するかといった新たな課題も生じる。
このように、反対派の一部は、「同姓が良い」という信念ではなく、「制度として崩すと不都合が多い」というシステム上の合理性を重視している。
その主張には一考の価値がある。
制度は更新できる「構造」であり更新し続ければならない
しかし、制度の整合性や運用コストといった問題は、「変えてはならない理由」にはならない。
むしろ、それをどう変えていくかこそが制度設計の本質である。
制度はあくまで構造であり、絶対ではない。
制度を更新するには、当然手間もコストも発生する。
だが、それを理由に現状を固定し続けるなら、社会の変化は制度によって封じ込められることになる。
現代の多様な家族形態、個人の尊厳、ジェンダー平等、、、
そうした価値観が広がるなかで、「旧来の形式を守るために新しい問題を見て見ぬふりをする」ことの方が、むしろ社会全体にとって大きなリスクではないか。
制度とは、人々の暮らしを支える仕組みであり、人々の選択肢を狭める“信仰”であってはならない。


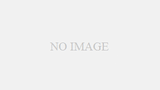
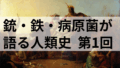
コメント