本能って、そもそも何?
「性欲は本能である」
この言葉は、あまりにも当たり前のように語られている。まるで「呼吸するように自然なもの」として、性欲の存在は人間の根源に据えられている。
しかし、ここで立ち止まって考えたい。
「本能」とはそもそも何なのか? それは本当に誰にとっても、どの時代にとっても、同じように“自然なもの”だったのか?
動物にとっての“本能”とは?
まずは教科書的な意味での本能を確認しておこう。
本能とは、学習によらず、生まれつき組み込まれた行動様式を指す。
ヒナ鳥が卵からかえった瞬間に親を追いかける、サケが生まれた川に戻って産卵する、ネコが獲物に飛びかかる──これらは誰にも教わらずとも繰り返される、遺伝的プログラムによる行動だ。
この定義に照らせば、人間の性欲もまた本能の一種とされてきた。
なぜなら、ヒトは種として子孫を残すために性的衝動を持つよう進化してきたからだ、という理屈だ。
でも、それって「どんな欲望」なの?
だが、次の瞬間に疑問が湧く。
本能としての性欲は、いったい「誰に」「どんなふうに」「いつ」「どのくらい」向かうのか?
そして、それは生まれた国や時代が違っても同じなのか?
仮に、性欲を「エネルギー」とするなら、それがどういう方向に流れるのか、どの出口を選ぶのかは、文化や社会の形に大きく左右されているように見える。
なぜある社会では異性愛が当然とされ、別の社会では同性への愛が尊ばれるのか?
なぜ一夫多妻が自然とされる時代があったのか?
なぜ性的なものが「恥」や「罪」と結びつけられる文化があるのか?
こうした違いを「全部、本能の範囲内」として説明するには、無理がある。
「食欲」や「睡眠」とは違う“ずれ”がある
性欲はたしかに生理的欲求だが、「お腹がすいた」「眠い」とは違って、誰かに向けられる。
そしてその“誰か”は、男か女か、年齢か、美的条件か、社会的地位か──つまり、性欲は対象選択を伴うという点で、単なる“衝動”とは違う。
それは「何を求めているのか」が文化によって定義される欲望でもある。
本能という言葉の“神話性”
ここまでくると、「性欲=本能」という言葉の便利さ、そしてその危うさが見えてくる。
なぜなら、「本能だから仕方ない」と言われれば、それ以上の問いは封じられてしまうからだ。
だが実際には、性欲のあり方は多様で、文化的で、歴史的な産物でもある。
ならば「本能」とは、もしかすると──
社会がある欲望を“自然”で“正しい”ものとして保証するために用いる、もっともらしい装置ではないだろうか?
でも、誰に?どうやって?──“欲望の方向”は誰が決めた?
前章で、性欲が「生まれつきの衝動」ではあっても、その向き先──「誰に向かうのか」は、実は自明ではないという話をした。
ここではでは、その問いをさらに掘り下げていく。
「なぜ自分は異性に惹かれるのか?」
「なぜ同性に惹かれる人がいるのか?」
そして──
「もし生まれた国や時代が違ったら、惹かれる対象も変わっていたのか?」
という、根源的な疑問に向き合う。
武士たちの恋愛対象は「少年」だった
たとえば日本の武士階級には、今では少し信じがたいような文化があった。
それが「衆道(しゅどう)」──男性同士の性愛関係だ。
特に年長の武士と若年の美少年(稚児)とのあいだで恋愛や性的な関係が公然と行われ、 「恋文の書き方」「夜伽の作法」「別れの儀礼」までがマニュアル化されていた。
このような関係は、単なる「儀礼」や「上下関係の延長」ではなく、本気の恋愛としても記録に残っている。
もし彼らが現代の日本に生まれていたら、異性愛者として家庭を持っていたかもしれない。
だが、当時の文化においては「同性を愛することが“美徳”として教えられていた」のだ。
欲望は“感じる”のではなく“教わる”?
この事例は一つの仮説を示唆する──
もしかすると、私たちが誰に惹かれるか、という“欲望の回路”は、ある程度文化によって配線されているのではないか?
たとえば:
同性愛が当たり前の文化で育った人は、同性への親密感が恋愛と結びつきやすくなる 異性愛しか認められていない文化で育った人は、同性に惹かれる感情に自覚すら持たないかもしれない
つまり、「惹かれること」が本能的に起こるのではなく、どこに惹かれるかの“意味づけ”を社会が与えているということ。
古代ギリシャでも同性愛は“教育”だった
似たような例は世界中にある。
古代ギリシャの都市国家では、年長の男性が少年に知識や礼節を教えながら性的な関係を持つことが、教育の一環とされていた。
ここでも、「男が男を愛する」ことは、社会的に推奨された“正しい欲望”だった。
現代社会でこれをやればスキャンダルだが、当時の価値観ではむしろ「大人の証」「精神的な成熟」だったのだ。
ならば「性的指向」も社会が作るのか?
この問いはとてもデリケートだ。
「性的指向は生まれつきだ」という主張は、同性愛者やトランスジェンダーの存在を正当化するために重要な意味を持ってきた。
しかし同時に、「欲望の方向性はすべて先天的だ」と言い切るのもまた、現実とずれているように思える。
なぜなら、ある文化では恋愛対象だったものが、別の文化では“ありえない”とされる──そんな事例があまりにも多いからだ。
「欲望の本能」は“方向”ではなく“熱量”かもしれない
ここまでの流れから言えるのは、こうかもしれない。
性欲という熱量はたしかに本能的だ。
だが、その熱を“誰に注ぐか”という回路は、文化が作っている。
つまり、欲望そのものは自然でも、その方向性や表現は社会に“しつけられている”のだ。
“社会がつくった本能”という逆説
ここまで見てきたように、人間の性欲にはたしかに「自然に湧き上がる衝動」としての側面がある。
その一方で、「その欲望をどこに向け、どう表現するか」は明らかに文化や社会によって規定されている。
ここで浮かび上がるのが、奇妙な逆説だ。
『性欲は“本能”とされているが、その本能自体が社会によってつくられているのではないか?』
ここでは、この逆説に向き合ってみる。
「本能」は誰が決めるのか?
たとえば、「性欲は本能だ」と言われると、私たちはつい納得してしまう。
だが、それは誰が決めたのだろう?
そして、「本能だから仕方ない」と考えた瞬間、何が隠されるのだろう?
この問いに最も鋭く挑んだのが、20世紀フランスの思想家ミシェル・フーコーである。
性は“発見”ではなく“発明”された
フーコーは『性の歴史』という著作の中で、こう述べた。
「私たちは“性”というものを抑圧してきたのではない。むしろ“性”を語りすぎ、制度化してきたのだ」
つまり彼は、性にまつわる自己認識(同性愛者、異性愛者、性的倒錯者など)は、近代になってから医学、心理学、法律、宗教が“性とは何か”を定義しはじめた結果、生まれた概念にすぎないと喝破した。
たとえば:
中世には存在しなかった「ホモセクシュアル」というカテゴリが、19世紀以降に医療用語として登場する 性的指向や性癖をラベリングすることで、“正常”と“逸脱”が線引きされる 結果として、人々は自分の性を「本能だ」と信じ込むようになる
→ 本能とは「発見」ではなく、「発明」されたのだ。
本能を“自然”に見せる社会の仕掛け
フーコーの示唆はこうだ
「本能だから自然だ」と私たちが信じているその構図こそ、社会が作り上げた制度的な装置である。
たとえば──
性的欲望を「抑えろ」と言う宗教は、その欲望を“あるもの”として前提化している 性教育や性犯罪の取り締まりも、「どういう性が正常か」を決める規範装置となっている メディアや広告は「性を消費すべきもの」として日常に流し込み、欲望の演出を行っている
こうして、性欲は“社会によって与えられた本能”として、私たちの中に埋め込まれる。
欲望は、湧き出すのではなく、誘導される?
ここで立ち止まって自分に問い直してみよう。
なぜ自分は異性を「魅力的」と感じるのか?
なぜ胸や太ももに視線が向かうのか?
なぜ恋愛と性欲をセットで考えるのか?
──それは果たして、「生まれつき」だったのか?
それとも、そういう“感じ方”を社会が提供してきたのではないか?
本能の正体は、「自然に思えるよう仕組まれた脚本」
そう考えると、「本能」という言葉は、ある欲望を社会的に正当化するための装置ともいえる。
「性欲は本能だ」というとき、それは“抑えがたい衝動”というより、“抑える必要がないとされる衝動”という意味で使われている。
しかし、その“正当な欲望”の枠組みを決めているのは社会であり、時代であり、私たちが生きる「語りの脚本」なのだ。
では「本能が変わる」のか?
これまで、性欲が“本能”とされながらも、その方向性・感じ方・表現の仕方が文化に深く依存していることを見てきた。
ではここで、核心に踏み込もう。
『もし私が違う文化に生まれていたら、同性に惹かれていたかもしれない?あるいは性的な感情そのものの対象が変わっていた?』
この問いに「はい」と答えることは、人間の「自己」や「欲望」がどれほど環境にかたちづくられているかを探る鍵となる。
性的指向も、性自認も、最初から「決まっている」わけではない?
現代の性科学では、「多くの人にとって性的指向は安定している」とされる。
しかしそれは、一度“自覚されたあと”に安定するという意味であって、
「生まれた瞬間から固定されていた」というわけではない。
特に性自認(自分を男性・女性・それ以外と感じること)や恋愛対象の“発見”には、以下のプロセスがある
自分の感じ方に名前を与える「語彙」があるかどうか 他者と比較して違和感に気づく「参照枠」があるかどうか 社会が「その感じ方はアリだ」と受け入れる空気があるかどうか
つまり、「誰に惹かれるか」や「自分を何者と感じるか」は、環境の中で“開かれる”可能性でもある。
武士が「衆道」を自然に思えた理由
武士が少年への性愛を自然に感じられたのは、
「生まれつきそうだったから」ではなく、“それが自然とされる文化”の中で自己を形成していたから。
社会が「男を愛することは美徳だ」と教え、 先輩たちが実践し、 自分もその中で“愛するとはこういうことだ”と理解する。
その流れの中で芽生えた感情や欲望は、たとえ後から見れば“変わり得る”ものであったとしても、本人にとっては“リアル”で“自然”だった。
「本来の自分」なんて、最初からない?
ここで問い直したいのは、そもそも──
「本当の私はこういう人間だったはず」という“本来性”は実在するのか?
文化・言語・教育・周囲の期待の中で育ち、何を良いと感じ、何に惹かれ、何を恥じるかという感性が形づくられるとき、私たちの「性の自己理解」も、後から書かれた脚本を自分の声で読み上げているようなものではないか。
すると、こう言えるかもしれない。
「性の本能が変わる」のではなく、“本能”という言葉で呼ばれる何かが、そもそも変化の中で育っていた。
欲望は選べないが、育つ環境は選べてしまう
これは、ある意味で怖い真実でもある。
あなたが異性愛者であるのは、先天的な脳の構造かもしれない。 でも、違う世界にいたら、同性への欲望が芽生えていたかもしれない。 そしてそれは、今のあなたの“真逆”ですらあるかもしれない。
その事実は、性的欲望や性自認を「本能」や「自己の核」として考える視点を、根底から揺さぶる。
「性」は自然か?文化か? いいえ、“どちらでもある”
ここまで、性欲や性的指向、性自認といった「性」にまつわるテーマについて、「本能か?文化か?」という視点で丁寧に解きほぐしてきた。
性欲はたしかに生理的衝動として「本能」のように感じられる。 しかし、それが「誰に」「どう向かうか」は文化が脚本を与える。 自分が何者であるかという性自認や欲望の方向性は、環境によって“開かれたり”“閉じられたり”する。
この旅の終点で、あらためて問い直したい。
『結局、“性”とは自然なものなのか?それとも社会が作り上げた幻想なのか?』
性は「自然のふりをした文化」でもあり、「文化に包まれた自然」でもある
この二項に対して、答えはどちらでもある。いや、どちらでも“しか”ない。
性欲という「熱」は、本能的に備わっている。 だがその「熱」をどこに注ぐか、どう意味づけるかは、文化によって決まる。
たとえるなら:
『性欲とは“火種”のようなものであり、その火が“どんな薪に燃え移るか”は文化が用意する。』
同じ火でも、焚き火になるか、囲炉裏になるか、火事になるか──それを決めるのは社会であり、環境であり、物語だ。
「本当の自分」を知ることは、脚本の存在に気づくこと
私たちは、自分の性のあり方を「これが本当の私」と感じる。
そしてその感覚はたしかにリアルで、否定されるべきものではない。
だがその一方で、
『「本当の私」が“与えられた脚本”によって演じられている可能性に気づくことも、成熟の一歩である。』
それは自己を否定することではなく、むしろ「なぜ自分はこう感じるのか?」と問い続ける力を手に入れることだ。
性をめぐる分断の時代にこそ必要な視点
現代は、性の多様性を認めようという動きと、それに反発する動きが交錯する混乱の時代でもある。
その中で、
「性は本能だから変えられない」vs「性は選べるからこそ尊重されるべきだ」
という論争が起きがちだ。
だが本稿の議論が示す通り、性は「変えられないもの」であり、「変わりうるもの」でもある。
それは生まれつきでもあり、育ちの産物でもある。
この両義性を理解することができれば、他者のあり方を「不自然」「間違い」と切り捨てることは、もはやできなくなる。
性とは、“生きる物語”そのものだ
最終的に、性とはこう定義できるかもしれない。
性とは、「生まれ持ったもの」と「与えられたもの」が交差する場所に、ただ一つの“私という物語”として立ち上がる、生きた現象である。
だからこそ、「本能か文化か」という問いに決着をつけるのではなく、
両者のあいだで“揺れる自分”を見つめること自体が、すでに深い自己理解の一歩なのだ。
欲望は姿に宿るか?──ヒトを見ずに宇宙人に育てられた少年の思考実験
ある日、地球の男の子が宇宙人に連れ去られた。
人間はおろか、女性という概念すら知らないまま、
その少年は遠い惑星で人類とはまったく異なる例えば“虫のような姿”の宇宙人たちに囲まれ、愛され、育てられた。
彼が大人になったとき、果たして何に性的な魅力を感じるのだろうか?
欲望は“本能”か、それとも“経験”か?
私たちはしばしば、「性欲は本能である」と言う。
だがこの思考実験が問うのは、“本能”とはどこまで先天的で、どこからが後天的か?”ということだ。
たしかに性欲という衝動自体は、生物学的に備わっている。 だが、「誰に」「どのように」向かうか
──つまり“欲望の対象”は、本当に生まれつき決まっているのだろうか?
少年は、人間の姿や地球の美的価値観を一切知らない。
彼が性的に惹かれる相手とは、自分を育ててくれたあの“虫のような外見”の宇宙人たちではないだろうか?
愛された“姿”が、欲望の起点になる
心理学や文化人類学の知見によれば、人間は性的対象を「学ぶ」傾向がある。
幼少期の愛着、スキンシップ、親密な関係性──そうした体験が、「この存在は安全」「好ましい」と身体に刷り込まれていく。
一部の性的嗜好(フェティシズムなど)も、無意識下の経験や結びつきから形成される。
つまり、“好きになる身体”とは、本能というより“記憶に刻まれた関係性の形”なのだ。
だからこそ、少年にとってあの宇宙人たちがいかに異形であっても、
「もっとも身近で愛された形」として、欲望の回路に接続される可能性は極めて高い。
「虫の姿」は人類の“進化的嫌悪”の対象ではないか?
ここでひとつの反論が浮かぶ:
「とはいえ虫は気持ち悪い。グロテスクなものに嫌悪感を持つのは、動物として当然では?」
この疑問に対し、進化心理学からはこうした仮説が出ている。
人類がまだ原始の環境にいた頃、クモやムカデ、寄生虫などの節足動物は病気や毒の媒介者として危険だった。 そのため、多足・節・ぬめり・不規則な動きなどに対する「嫌悪感」は、危険を回避するために進化的に埋め込まれた可能性がある。
つまり、私たちが虫に「うっ」となるのは、文化ではなくDNAレベルの警報かもしれない。
それでも欲望は“乗り越える”
しかし、人間の心はそれほど単純ではない。
嫌悪感は“感じない訓練”ができる。 恐怖の対象を「美しいもの」と再構成する文化的な力もある。 特撮ヒーロー(仮面ライダー=バッタ)や、虫モチーフの擬人化キャラに魅力を感じる例もある。
つまり、進化的嫌悪は障壁ではあるが、絶対的ではない。
関係性・経験・文化が十分に積み重なれば、“虫すら愛の対象になりうる”。
カフカの『変身』のザムザとの逆説的な交差
この話は、カフカの『変身』と奇妙な対話を始める。
ザムザは姿が“虫”になっただけで、家族に捨てられた。 だがこの少年は、“虫の姿”しか知らないまま、そこに愛を見出す。
どちらも「身体が異なること」が、関係性を変えてしまうか否かをめぐる物語である。
そしてこの思考実験は、『変身』とは真逆の答えを提示する──
愛が最初に差し出された姿こそが、その人にとって“欲望の自然な形”になり得る。
欲望は姿に宿るのではなく、“記憶と関係”に宿る
少年が惹かれるのは、美でも性的特徴でもなく、
「この存在に抱かれてきた」
「守られてきた」
「安心を感じた」
という身体の記憶である。
それは外見がどうであれ、愛された経験が“魅力”に書き換えてくれる。
たとえそれが、虫のような姿であっても。


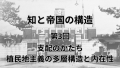

コメント