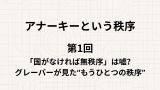国家は主体ではない。それは人間が歴史のなかで作り上げた制度にすぎない。
しかし多くの社会で国家は、意志や感情を持つかのように語られ、人格化された『権威』として振る舞う。サルトルの実存主義は、まさにこの構造を疑うための視座を与えてくれる。
国家が本質を装うとき、人は自由を手放す
「実存は本質に先立つ」という命題が示すように、サルトルはあらゆる『本質』を人間の自由の敵として扱った。
国家もまた例外ではない。国家が本質的な権威を持つかのように見えるとき、人は自らの自由と判断を国家に明け渡し、責任を外部へ転嫁してしまう。
実存主義から見れば、国家の権威化とは、人間が自由から逃れるために作り上げたもっとも巧妙な物語のひとつである。

ジャン=ポール・サルトルとは
20世紀フランスを代表する哲学者。
人間は外側から与えられた本質ではなく、選択と行為によって自分を形づくる存在だと考えた。
国家や伝統といった大きな枠組みに依存するのではなく、自分の自由を引き受ける姿勢を重視したんだ。
ボクの名前も、どこかでこの思想に触れて生まれた部分があるようなんだ。
国家暴力と『物語化された主体』としての国家
戦後のサルトルは、この構造が植民地主義や国家暴力の正当化にどのように利用されるかを鋭く批判した。
国家は暴力の独占装置であり、暴力を正当化するために「国民」「伝統」「誇り」といった物語を必要とする。
これらの語りは、国家を一つの主体として擬似的に立ち上げ、人々にその意志を代弁させる。
サルトルにとって、この人格化された国家こそ自由の最大の障壁となる。
国家を否定しないサルトル──暫定的な制度としての国家
しかしサルトルは単純な国家否定論に陥らない。
晩年の対話録では、国家が社会的調整や公共サービスの面で果たす役割を一定程度認めつつも、その正当性はつねに暫定的であるべきだと述べている。
国家が固定された権威として振る舞うのではなく、
人間の行為によって絶えず問い直され、再構成されるべき『装置』だという立場である。
国家の権威は『後付けの物語』である
実存主義の視点から見れば、国家の権威とは「本質の物語化」によって生まれる。
国家の意志、国家の利益、国家の誇り──これらは自然な属性ではなく、後から付与された意味づけにすぎない。
国家が主体のように扱われるとき、人は自己の自由を国家の名に委ね、その決断の責任から逃避してしまう。
サルトルが批判したのは、まさにこの態度である。

実存主義とは?
実存主義では、人間はあらかじめ決められた本質を持たず、まず世界に存在し、そこから自分の行為によって自分を形づくると考えるんだ。
サルトルはこの考えを説明するために、紙切りナイフのような道具を例に挙げた。
紙切りナイフは「紙を切る」という本質が先にあり、その目的に合わせて作られる。
でも人間は本質が先にあるわけではなく、選びと行為を通して本質を後からつくっていくんだ。
こうした視点が、「実存は本質に先立つ」という実存主義の中心にあるんだ。
国家を絶対化しない視点こそ、実存主義の核心
サルトルの実存主義は、国家を制度として扱う冷静な視座を与える。
国家は人格ではなく、人間の歴史的行為によって作られ、運用され、変形される集合体である。
国家の権威は自然に生まれるものではなく、人々の選択と合意によって構築される『相対的な構造』にすぎない。
だからこそ、国家の権威を疑うことは国家を否定することではない。
国家を絶対化せず、つねに自由の観点から読み直す姿勢こそ、実存主義が求める態度である。
国家がどのような権威として成立するかは、つねに私たち自身の自由にゆだねられている。
あわせて読む