「母系社会」と聞くと、女性が主導する平等で平和な社会を思い浮かべる人も多いかもしれない。実際、フェミニズムの文脈では、かつて存在したとされる“女性が中心の社会”が理想として語られることがある。しかし、母系社会とは本当に女性が支配する社会だったのか? 現代のフェミニズムにとって、母系的な価値観はどのような意味を持つのか?
本記事では、母系社会の実態とその制度的構造をひもときながら、ジェンダー平等や社会制度の可能性との関係を探っていく。
母系社会とは何か──母権制との違い
「母系社会」と聞いて、母親が家族の中心で支配的な存在となる社会を思い浮かべる人は少なくない。しかし、それは厳密には誤解を含む。学術的にいう「母系社会(matrilineal society)」とは、単に女性が家の権力を握る社会ではない。そこにあるのは、血統や親族関係を母方を基準に構築する制度であり、「女性の支配」とは限らないのである。
母系社会では、家系は母の血を通して継がれる。子どもは父ではなく母の一族に属し、財産や称号も母系のラインで受け継がれるのが基本である。このような社会では、たとえば母の兄(伯父)が家族内で権威ある存在となり、実の父親は比較的影の薄い役割を担うことも珍しくない。つまり、**母系社会とは「母親が支配者になる社会」ではなく、「親族関係と継承の構造が母方に依存する社会」**なのだ。
これとしばしば混同されるのが「母権制(matriarchy)」である。母権制とは、女性が社会の支配的地位にあり、政治・宗教・経済においても主導権を持つ体制を指す。いわば、父権制の“逆”の構造である。しかし、歴史的に厳密な意味での母権制が存在したと証明された例は極めて少ない。むしろ、多くの母系社会では親族構造が母方中心であっても、実際の権力は依然として男性(とくに母方の男性)に集中していることが多い。
たとえば、北米先住民のイロコイ連邦では、氏族の血統は母系で継がれ、女性たちが首長を任命・解任する権限を持っていたが、実際に首長となるのは男性であり、戦争や外交を担うのも男性であった。このように、母系社会は女性にとって相対的に地位が高くなる傾向はあるが、それがそのまま「女性による支配」に直結するわけではない。
フェミニズムの文脈では、しばしば「かつて女性が主導していた社会があった」という言説が語られるが、その多くはこの「母系」と「母権」の混同に基づいている。母系社会は、確かに女性の血統が重視されるが、それは生物的な確実性や出産の役割に基づく制度的合理性であり、「女性の解放」や「平等な社会構造」とはまた別の次元にある。
それでも、母系的な価値観が示すもうひとつの社会の形──それは、「支配と命令」ではなく「継承と関係性」に根ざした構造である。フェミニズムがこの構造に惹かれるのは、「父権的社会」の対抗軸というよりも、人間社会のあり方を問い直す視点のひとつとして、そこに制度的な想像力を見出しているからだと考えるべきだろう。

“母系社会”って、“お母さんがエライ”って意味じゃないんだよ。
あれは“誰の子か確実にわかる”っていう、人類の親族設計の合理性から来てるんだ。
だから、“母方の親戚が中心”ってだけで、“女王様が支配してた社会”とは限らないんだよね。
フェミニズムと母系社会──想像力と事実のあいだ
1970年代以降の第二波フェミニズムの文脈において、「母系社会」はしばしば理想的な過去として語られてきた。そこでは、かつて女性が平等に、あるいは主導的に社会を築いていたというイメージが繰り返し提示される。神話的なアマゾン、古代の女神信仰、出産と大地を結びつけた母なる文化――こうした物語は、現代の父権的社会とは異なる可能性を想像するための装置として、多くの思想家や運動家に支持された。
たしかに、「女神崇拝の時代」「女性中心の平和な農耕社会」といったモデルは、現代の支配と競争に満ちた構造への対抗軸として、強い魅力を放つ。だが、こうした語りは往々にして、実証的な人類学的知見と乖離している。現存する母系社会の多くは、女性が支配的なわけではなく、権力の多くは依然として男性、特に母方の男性に集中していることが多い。いわば「母系であっても母権とは限らない」という現実がある。
ここで重要なのは、母系社会を「歴史的事実」としてではなく、「制度的想像力」として捉える視点である。たとえばイロコイ連邦では、氏族の血統は母方で継承され、女性が首長の任命や解任に関与するなど、制度の根幹に女性の役割が明確に組み込まれていた。ここには単に「女性が偉い」ではない、社会制度としての多様性が存在している。
フェミニズムにとって、こうした母系的価値観は、「もうひとつの現実的な制度の可能性」としての意味を持つ。今ある社会構造が普遍でも自然でもないことを示し、支配や所有に基づかない関係性のモデルを提示する。それは、過去の幻想を懐かしむのではなく、現代の制度を問い直すための「外部」を手に入れる手段なのだ。
言い換えれば、母系社会はフェミニズムにとって過去の事実としてよりも、制度的な「対照実験」としての意義を持つ。父権制を批判するための理想郷ではなく、あくまで「人間社会には他の構造もあり得た」という前提を取り戻すための基準点である。

“アマゾンの女戦士”って話はギリシア神話だけど、黒海周辺のスキタイ系民族に実際そういう女性戦士文化があったかもって説もあるんだよ。
ロマンと現実って、完全に断絶してるわけでもないのさ。
母系的価値観が示すもうひとつの社会モデル
母系社会の実態が、理想化された「女性による支配社会」とは異なるとしても、そこに内在する構造には注目すべき点が多い。なかでも重要なのは、母系的な価値観が、現代の社会構造とは異なる“もうひとつのモデル”を体現しているという点である。
第一に、母系社会は継承の論理が個人の所有を超えている。たとえば財産や土地は、母から娘へと受け継がれ、個人ではなく一族全体が所有権を持つ形になる。これは、近代的な私有財産の発想とは異なり、共同体的な資源の管理と循環を可能にする。個人の蓄積による競争ではなく、血統と関係性に基づく社会的安定が前提となっている。
第二に、家族の構造においても、母系的社会では父親が家族の中心ではない。たとえば「母の兄」が権威を持つ構造では、実の父親の役割は限定的である。これは裏を返せば、父性的権威や性役割を絶対視しない柔軟性を持っているとも言える。男性中心の家父長制ではなく、役割が分散された親族ネットワークこそが秩序の基盤なのだ。
また、こうした構造は、フェミニズムの思想、特に「ケアの倫理(ethics of care)」とも親和性が高い。
これはアメリカの心理学者キャロル・ギリガンが提唱した概念で、
従来の男性的な「正義」や「原則」に基づく倫理とは異なり、人と人との関係性、具体的な文脈、配慮を重視する思考のあり方を指す。
母系社会は、まさにこのようなつながりと再生産の倫理を、制度として体現している点に注目すべきだろう。
さらに、近代的なヒエラルキー構造や国家のように、上意下達の命令系統ではなく、母系社会では水平的な関係性や循環性が強調される。
こうした特徴は、今日の分散型ネットワーク社会や脱中央集権的な組織論とも接点を持ち得る。
つまり、母系的価値観は、ジェンダー平等という枠を超えて、社会制度そのものの設計思想に別の道筋を示すのである。
もちろん、母系社会が現代にそのまま適用可能だとは限らない。だが、その価値観に内在する構造は、父系的社会が当然視してきた原則――所有・競争・支配――とは異なるもうひとつの基盤を提示している。そこにこそ、「母系的価値観がもたらす知的資源」としての本質がある。

母系社会って、女が偉いってより、つながりをどう維持するかって発想なんだよ。モノの所有よりも、関係の継承。競争よりも循環。
つまり、勝つか負けるかじゃなくて、つながるか切れるかで社会を考える設計思想なんだ。
母系社会の中の現実──理想と限界
母系社会がもうひとつの制度モデルとして注目されるのは、所有や支配ではなく、継承と関係性に基づく秩序を内包しているからだ。だが同時に、それを過度に理想化することには慎重であるべきだろう。実際の母系社会は、必ずしも平和でも自由でもなかった。
たとえば西アフリカのアカン族では、母系による血統継承が今も文化的に残っているが、そこでも政治的・軍事的な実権はしばしば「母の兄」など男性に集中している。北米のイロコイ連邦では、女性が首長の任命権を持っていたとはいえ、実際に外交や戦争を担うのは男性であり、社会の意思決定から女性が排除されない代わりに、「戦う役割」は依然として男性に委ねられていた。
また、アジアのミナンカバウ族では、母系継承を守りながらも、イスラム教という父系的宗教との折衷的な共存を強いられている。制度としての母系が残っていても、宗教・教育・法律といった領域では父系的価値観が優勢になりがちで、形式的な母系と実質的な父系の二重構造にあると言ってよい。
加えて、母系社会においても女性の自由が常に保障されていたわけではない。たとえば、モソ族の「通い婚(走婚)」がリベラルな恋愛観の象徴として語られる一方で、出産や育児の負担は一貫して女性に集中していた。そこにジェンダー的な平等があったとは言いがたい。
さらに、母系社会は「家」と「血筋」による結束を重視するがゆえに、家族の外部との関係が築きにくくなるという制約もある。母の血統によって社会的位置が決まるという構造は、裏を返せば閉鎖性や排他性を強める要因にもなりうる。とくに他集団との婚姻や同盟形成において、父系社会のほうが柔軟に機能してきた側面も見逃せない。
つまり、母系社会は「もうひとつの可能性」であっても「完成された理想社会」ではない。むしろ重要なのは、いかなる制度にも限界があり、それでも制度を問い直すことに意味があるという点である。
母系的価値観は、現代の制度を否定するための武器ではない。むしろ、制度とは歴史的・文化的な構築物であり、問い直しが可能であるという事実を示す存在なのだ。理想の対極としてではなく、現実の中に埋め込まれた複雑な構造として、母系社会を見つめ直す必要がある。
おわりに──母系的価値観の再発見は社会の柔軟性を示す
母系社会の実態を見れば、それが決してユートピアではなかったことは明らかである。そこには不平等も、階層も、役割の固定もあった。幻想を突き崩せば、見えてくるのはやはり人間の社会が持つ構造の重力だ。
だが、それでもなお、母系的価値観は重要である。なぜなら、それは**「別の構造が可能だった」という事実の痕跡**だからだ。
人類の歴史において、制度や価値観が一枚岩であったことは一度もない。父系的な秩序が主流となったのは、戦争・宗教・国家制度といった力の合理性と接続しやすかったからにすぎない。裏を返せば、母系社会はそれらの力と親和性が低かったがゆえに、支配構造の中心から外れていったとも言える。
だが、社会の進化とは必ずしも戦争と中央集権の論理だけで動いてきたわけではない。母系的な制度に内在していた「関係性の重視」や「資源の循環」、「権力の分散」といった発想は、現代社会においてもなお、制度設計や価値の再構築において示唆的であり続けている。
重要なのは、母系社会を過去の理想として懐かしむことではない。そうではなく、母系的な価値観が存在していたこと自体が、我々の社会制度が唯一のかたちではないという事実を証明している。その意味で、母系的価値観は過去ではなく、「制度の選択肢としての未来」に関わる。
支配の逆転ではなく、制度の柔軟性。秩序の固定ではなく、関係性の設計。
母系社会はそれを完全に実現したわけではないが、少なくともその可能性を一度、かたちにしたことがある。その記憶が、制度を「問うことすら許されないもの」ではなく、「見直すことができるもの」へと引き戻してくれる。
社会に必要なのは、絶えず構造を問い直す想像力である。

制度って、それしかないように見えて、実はけっこうバリエーションあるんだ。
母系社会はそのひとつ。
消えたわけじゃなく、選ばれなかっただけ──今までは、ね。



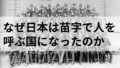
コメント