「正しい日本語を使いましょう」「標準語で話しなさい」。
こうした言葉の裏には、無意識のうちにある“言語のヒエラルキー”が潜んでいる。
だが本来、言語とは誰かの所有物ではなく、人々のあいだに生まれ、受け継がれ、変化していく共有財のようなものだったはずだ。
この回では、国家が整備した「標準語」と、それによって周縁に追いやられた方言・少数言語の歴史に目を向け、言葉が「誰のものなのか?」という根源的な問いを見つめ直してみたい。
言語は「共通のもの」であるはずが…
言葉は、人と人が意思を伝え合うために生まれた。
つまり本質的には、誰かと共有するためのツールであり、本来、誰の“所有物”でもなかったはずである。
しかし現実には、多くの社会で言語は「正しさ」を伴って語られる。
「正しい言葉を使いましょう」「正しい敬語で話しなさい」「文法的に正しくない」。
こうした言説のなかで、言葉は共有財ではなく、秩序を保つルールとして機能しはじめる。
さらにややこしいのは、「正しい言葉」がしばしば「偉い人の言葉」になっていくことである。
- 教科書に載る言い回し
- アナウンサーが使うイントネーション
- ビジネスの場で推奨される語彙や敬語
こうした「規範とされる言葉」があることで、人々は自分の話し方に無意識の優劣を感じるようになる。
たとえば、方言を話すと「なまってるね」と言われる。
そこには「標準」が基準にあり、「それからズレている」という前提がある。
だが、ここで立ち止まって考えてみよう。
そもそも“標準語”とは、誰が決めたものなのか?
なぜそれが、「正しい言葉」と見なされるようになったのか?
言葉は本来、多様であって当たり前のものだった。
それを「正しいか/間違っているか」という二項で測ること自体が、近代以降の政治的・教育的な枠組みによって作られた考え方なのだ。

標準語(共通語)は、どの国でも「中立な言葉」として作られたわけではないんだ。
たとえばフランス語の標準語は、パリ地方(イル=ド=フランス)の方言がベース。
地域的な“勝者の言葉”が、そのまま「国の言葉」として押し広げられていったケースが多いんだよ。
標準語は誰のために整備されたのか?
標準語は、最初から「国民全体のため」に設計されたわけではない。
むしろ多くの国では、政治や軍事、行政の効率を目的として、特定の言語形が“標準”に押し上げられていった。
たとえば日本の場合、明治以降の近代化政策で「言文一致運動」が起こり、東京山の手の言葉をベースに標準語(共通語)が整備された。
この背景には、次のような現実的な動機があった
- 軍隊で命令が通らない(地方ごとに言葉が違いすぎる)
- 全国で同じ教科書を使いたい(教育の統一)
- 官僚制度を動かす共通の行政言語が必要
つまり、統治と教育のために言語が「単一化」されたのである。
同じ構図は他国にも見られる。
- フランス語:パリ近郊の言葉(イル=ド=フランス方言)が「正しいフランス語」とされ、他の地方語(オック語など)は排除された。
- スペイン語:カスティーリャ語が「スペイン語」として整備され、カタルーニャ語やバスク語は長らく抑圧された。
- アラビア語:口語は地域ごとに大きく異なるが、標準アラビア語(フスハー)は古典語を基に人工的に整備された文語である。
これらの「標準語」には共通点がある。
それは、中央集権的な国家形成とセットで生まれたということだ。
また、標準語はしばしば「美しい」「論理的」「上品」などの価値が付与される。
だがそれは後づけされたイメージであり、本質的な言語の優劣ではない。
むしろ、標準語の整備とは「交通のための道具」だったはずが、いつしかアイデンティティや社会階層を区別する装置へとすり替わっていった。
コラム:なぜ東京(江戸)の言葉が「正しい日本語」になったのか?
明治時代、標準語のモデルとして採用されたのは東京・山の手の言葉だった。
だが、なぜ「勝者」である薩摩弁や長州弁、あるいは皇居のあったの京都弁が選ばれなかったのだろうか?
そこには、単なる政治的力関係だけでなく、言葉の「機能性」と「象徴性」のバランスがあった。
- 薩摩弁・長州弁は、統治の中枢を担ったとはいえ、発音や語彙に強いクセがあり、他地域の人間には聞き取りが困難だった。教育や軍隊の共通語としては不向きだった。
- 一方、京言葉は格式の面では理想的だったが、日常言語としてはかけ離れすぎていた。
天皇の「言葉」はあくまで“神聖なもの”として、象徴性を保ったまま置かれた。
そうして現実的な選択肢として残ったのが、行政・出版・教育の中心地であり、文化的にも洗練されていた東京の山の手言葉だった。
つまり、標準語は「最も強い言葉」ではなく、「最も“使いやすくて都合のいい”言葉」として選ばれたのである。
抑圧された言語たち──方言、少数言語、植民地言語
標準語が国家によって整備される一方で、その影で“標準ではない言葉”が切り捨てられていった。
それは単なる言葉の淘汰ではなく、文化や記憶、アイデンティティの喪失をも意味する。
たとえば日本では、明治以降の教育制度において、地方の子どもたちは「方言札(方言罰札)」をかけられた。
学校内で方言を話すと罰を受けるというこの制度は、地方言語を“恥ずべきもの”として内面化させたのである。
同じ構図は世界中に見られる。
- ウェールズ語は、イギリス政府の教育政策で徹底的に排除され、一時は消滅寸前に追い込まれた。
- バスク語やカタルーニャ語は、スペインのフランコ政権下で使用が禁じられた。
- アメリカ先住民の言語も、寄宿学校制度によって英語教育が強制され、世代間伝承が断たれた。
これらの言語に共通するのは、単に“使われなくなった”のではなく、“使わせてもらえなかった”という点である。
さらに、植民地支配のもとでは、支配者の言語(フランス語、英語など)が「文明の言語」として押し付けられた。
- フランス領アフリカでは、仏語を話すことが「知性」と「市民権」の象徴とされ、現地語は“野蛮”とされた。
- 日本の朝鮮・台湾統治でも、現地の言語は抑圧され、日本語が“国語”として強制された。
つまり、言語の抑圧とは文化の抑圧であり、個人の記憶や共同体の歴史を切断する暴力でもあったのだ。
コラム:言語の“狭さ”は地理で測れない──エストニア人の妻がうんざりする質問
「バルト三国って、あんなに狭いのになぜ言葉は違うんですか?」
日本で暮らしていると、こうした質問をエストニア人の妻がたびたび受ける。
彼女にとっては、もうすっかり「うんざりする定番」のひとつらしい。
確かに、日本人の感覚からすれば不思議かもしれない。
日本はそれなりに広い国土を持ちながら、ほぼ全国で共通の言葉を話している。
だから、バルト三国のように日本の本州よりはるかに小さい地域に3つの異なる言語が並立しているという事実は、「言葉ってそんなに分かれるもの?」という素朴な疑問を誘ってしまうのだろう。
しかし、これはむしろ逆だ。
「狭いのに言葉が違う」のではなく、普通は「違って当然」なのだ。
世界の多くの地域では、山や森、海などの自然障壁に囲まれた集落ごとに異なる言語が形成される。
交易が少なければ、言葉はそれぞれの土地で独自に進化する。
それが自然な姿であり、むしろ日本のように全国で“同じ言葉”が通じる方が、世界的には珍しい。
日本の標準語が、明治以降の教育制度や軍隊、メディアによって急速に“上書きされた共通語”であることを忘れてはいけない。
つまり、
「狭いのに言語が違う」ではなく、「広いのに言語が一つ」こそが例外的現象なのである。
エストニア語、ラトビア語、リトアニア語は、そもそも言語族すら異なる。
言葉を共有することより、違いを保ち続けることが、それぞれの民族の“生き延び方”だった。
妻が笑いながらも眉をひそめるその質問には、無意識のうちに、「言語=国家=一体」という、日本独特の思い込みが見え隠れしているのかもしれない。
※ エストニア語はフィンウラル語族で、諸説あるが、1説では日本語と同じアルタイ語族ともいわれている。言語の距離感ではインドヨーロッパ語族のドイツ語や英語よりもむしろ日本語のほうが近い。
言語のアイデンティティ──失われた言葉、取り戻された言葉
かつて「劣った言葉」として葬られそうになった言語が、
今では“誇るべき文化遺産”として蘇ろうとしている──そんな事例が、世界にはいくつもある。
抑圧から復興へ──ウェールズ語とヘブライ語
たとえばウェールズ語。
20世紀前半まで徹底的に排除されていたこの言語は、教育政策や運動により復権し、現在ではウェールズ政府の公用語としても使用されている。子ども向け番組や学習教材も整備され、話者は徐々に回復しつつある。
あるいはヘブライ語。
紀元前後に日常使用が絶え、「死語」になったとされていたこの言語は、
近代以降、ユダヤ人国家建設とともに国家語として“復活”を遂げた。
これは単なる言語の再利用ではなく、民族アイデンティティそのものの“再起動”である。
小さな言語が守ろうとするもの
こうした例に共通するのは、言語が単なるコミュニケーション手段ではないという点だ。
- 言語は、その土地で育まれた価値観や感情の型、語りのリズムを宿している。
- だからこそ、「言葉を守る」とは、「その共同体の生き方そのものを守る」ことにつながる。
近年では、少数言語を「文化遺産」として保護する機運も高まっている。
ユネスコは世界中の危機言語をリスト化し、保存活動や教材開発を支援している。
また、地域ごとの言語復興運動(Language revitalization)も進んでいる。
国家と言語の関係が“固定”でなくなる時代へ
インターネットや移動の自由化により、1つの国家=1つの言語という前提が崩れつつある。
- 多言語話者の増加
- オンライン上での少数言語コミュニティの活性化
- 翻訳技術による言語の壁の低下
言葉は、国家ではなく、人に帰属する時代に入りつつある。
それは、言語が再び“個人と地域のもの”として多様に咲き直していく可能性でもある。

実は日本にも「再言語化」って動きはあるんだ。
アイヌ語や琉球語みたいに、かつて“消されかけた言葉”をもう一度取り戻そうとする流れね。
でも、日本じゃそれがなかなか表に出づらい。
というのも、この国では「日本語=国語=みんなの言葉」って感覚が当たり前になってるから、そこから外れる言葉は、“方言”とか“昔の言葉”みたいに扱われがちなんだ。
大陸国家みたいに、「国家と言語が別」でも違和感がない社会と違って、日本ではどうしても「共通語の外=国の外の話」って空気がつきまとう。
言葉を守るって話が、「文化」じゃなくて「郷土愛」止まりで片付けられちゃうのも、
ちょっとした構造のクセなんだよね。
言語は“共有財産”か、それとも“所有物”か?
言葉は誰のものなのか──この問いは、単なる言語学の問題にとどまらない。
それは文化の継承と個人の自由、社会の包摂と差別の構造に関わる、きわめて現実的な問いでもある。
言語ポリシーが問う“誰のものか”
たとえば、公教育での言語使用。
- 少数民族の子どもたちに対して、共通語だけで教育するのか?
- 母語での学習機会を保障すべきか?
これは、単に効率の問題ではなく、アイデンティティの尊重と権利の問題である。
国や自治体が「何語を公用語にするか」を決めるとき、
そこには「この社会に“属していい人”の定義」が隠れている。
つまり、言語政策とは「国語教育」以上に、「国民とは誰か」を問う行為でもあるのだ。
言葉が“奪われる”という経験
一部の言語は、「使ってはいけないもの」とされた歴史を持つ。
- アメリカのネイティブ・アメリカンの多くの言語
- 日本国内のアイヌ語・琉球諸語の排除
こうした事例では、「言葉を失うこと」は、単なる不便ではなく、“文化的記憶”や“共同体とのつながり”の喪失を意味する。
その言葉でしか語れない物語があり、
その言葉でしか表現できない感情がある。
言語を奪われることは、人生を“翻訳不能な何か”に置き換えられてしまう痛みなのだ。
言葉を共有する社会、分けあう社会へ
現代の社会では、
「正しい言葉を話せ」というプレッシャーと、
「自分の言葉で話したい」という欲求が、せめぎ合っている。
グローバル化とローカリズムがぶつかり合う中で、
言葉は「矯正」されるものではなく、“分けあう”対象として見直されつつある。
- 公用語とは別に地域言語をサポートする政策
- 多言語表記や字幕、音声読み上げなどのアクセシビリティ対応
- SNSや動画文化の中で生まれる“脱正規”の新しい表現
こうした動きは、言葉が「所有物」から「共有の財産」へと移りつつある兆しかもしれない。

言葉ってさ、ほんとは「誰のもの」って決められないんだよね。
権力がルールを決めても、使う人たちが勝手に揺らしていく。
つまり“勝手に生きてる”んだ、言葉ってやつは。
だからこそ、声の小さい人の言葉にも、ちゃんと耳をすませたいんだよな。
「変化」を怖がるより、「届く場所が広がる」って考えたほうが、ボクは好きなんだ。
シリーズ:言語はなぜ崩れるのか?
- 自然言語はなぜ崩れるのか?
- なぜ発音とスペルはズレていくのか?──英語とフランス語の“不一致”を解剖する
- 言語は崩れるほうが強い?──不規則性が生む柔軟性と多様性
- 今読んだ記事→ 言葉は誰のものでもある──共通語とマイノリティのせめぎあい
- 言語はなぜ崩れるのか?──まとめ
- 正しさは誰が決める?──言語規範と“誤用”という幻想


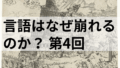
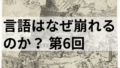
コメント