言語は変化する──それはもはや前提として受け入れられている。
だが、その変化は必ずしも“崩壊”や“劣化”を意味するのだろうか?
たとえば、文法の例外、不規則な動詞、意味の揺れ。
一見すると非効率で混乱の元に思えるが、
実はそうした“不規則さ”こそが、言語の柔軟さや多様性の源であるという考え方もある。
この回では、「言語が崩れていくこと」が、
むしろ“強さ”や“適応力”につながるという視点から、
不規則性の意義とその働きを考えていく。
不規則性は“バグ”なのか?
言語を学ぶ者にとって、不規則な表現ほど厄介なものはない。
不規則動詞、不規則複数形、不規則な活用。
どれも一つひとつ暗記するしかないように思える。
それはまるで、整ったシステムに紛れ込んだバグ(欠陥)のようだ。
だが、ここで立ち止まって考えてみよう。
なぜ世界中の言語には、そんな“バグ”が自然発生的に存在するのか?
そして、なぜそれが完全には消えずに残っているのか?
例外だらけの英語と、例外のないエスペラント
たとえば英語は、不規則動詞の宝庫だ。
- go → went
- eat → ate
- bring → brought
これに対して、人工言語のエスペラントにはほとんど例外がない。
すべての動詞は -as(現在形)で終わり、-is(過去)、-os(未来)と整然としている。
単語の派生も規則的だ。
その結果、エスペラントは非常に学びやすい。
だが同時に、“不自然”とも感じられることがある。
ネイティブにとっての言語とは、暗記や計算で処理するものではなく、
リズムと直感で反応するものだ。
規則性が高すぎると言語は“無味乾燥”になりやすく、
柔らかさや遊びの余地がなくなるという声もある。
不規則性は“使用頻度”と関係している?
言語学では、よく使う語ほど不規則性が維持されやすいという説がある。
- 「go」や「be」などの基本動詞ほど不規則で、
- 「download」や「email」のような新語は規則的
これは、頻繁に使われる語は話者の記憶に深く根付きやすく、変化に強いためだとされる。
逆にあまり使われない語は、文法の一般的なパターンに吸収されて規則化していく傾向にある。
つまり、不規則性は偶然の遺物ではなく、“頻度”という合理的な軸で維持されている可能性があるのだ。

不規則って、たしかに面倒だけどさ。
でもそれって、ただの間違いじゃなくて、人が長い時間かけて使い込んできた痕跡なんだよね。
ピシッと整ってないぶん、そこに“らしさ”がにじむっていうかさ。
非効率に見えて、じつは一番リアルってやつかもね。
不規則性がつくる「揺らぎ」と「余白」
不規則な文法や曖昧な語義は、言語の正確さを損なう――
それは教育の場ではよく聞かれる考え方だ。
しかし一方で、こうした「揺らぎ」がなければ、言語は機械の命令文のように乾いたものになってしまう。
不規則性や曖昧さは、表現の幅とニュアンスの豊かさを可能にする構造なのだ。
定義の“曖昧さ”が生む解釈の幅
たとえば日本語の「やさしい」という語。
- 「簡単」という意味でも使われるし、
- 「親切」「穏やか」といった意味でも用いられる。
このような曖昧さは、状況や文脈に応じてニュアンスを自在に操る余地を生む。
定義がグレーだからこそ、読み手や聞き手の解釈が働く。
語の意味が完全に固定されていれば、こうした“言葉の間”は生まれない。
例外表現が文化を生む
日本語における敬語や助詞、英語におけるイディオム、フランス語の性と数の一致など――
多くの言語に存在する一見非合理な仕組みは、しばしばその言語の文化的なアイデンティティを形成する。
- 英語の “kick the bucket”(死ぬ)や “spill the beans”(秘密を漏らす)のようなイディオムは、直訳では意味が通らないが、言語にユーモアや比喩の層を与えている。
- 日本語の「〜させていただく」は、動詞の尊敬形にさらに謙譲のニュアンスを加えるが、この過剰とも思える言い回しが、日本語の距離感と配慮の文化を表現しているともいえる。
不規則性や曖昧さは、そうした“文化のにじみ”の温床となる。

言葉って、ただの伝言ゲームじゃないんだよね。
感情とか空気とか、うまく言えない“何か”をのっけるためには、ちょっとくらいズレてるほうが都合がいいんだ。
ルール通りにしか動かない言語は、たぶん人の気持ちには不向きなんだよ。
不規則性は“進化”の伏線か?
不規則性や曖昧さは、単なる混乱の種ではない。
それは次の変化を準備する“ゆるみ”かもしれない。
自然言語は、数学のように確定した論理で運用されるものではない。
時代、文化、社会構造によって、常に意味や構文が変化していく。
そしてその変化の種は、多くの場合、「不規則性」の中に潜んでいる。
崩れかけた表現は、新しい形への足がかりになる
言語には、曖昧な文法構造や使い方が定着していく過程がある。
たとえば日本語の「ら」抜き言葉。
- 「見られる」→「見れる」
- 「来られる」→「来れる」
文法的には“誤り”とされてきたが、実際には多くの話者が日常的に使っており、
すでにある程度の市民権を得つつある。
こうした変化は、言語の崩壊ではなく、柔軟な再構成=進化と見ることもできる。
英語における文法の“簡略化”
古英語(Old English)には、屈折変化(語尾変化)や格の区別が多くあった。
ところが中英語、近代英語を経て、これらの多くが省略・簡略化されていく。
- 動詞の人称変化の簡略化
- 名詞の複数形の一般化(複数形が -s に統一されていく)
- 語順に依存した構造への移行
つまり英語は、かつて“複雑だった”構造を自ら脱ぎ捨て、わかりやすく変化した歴史を持つ。
この「崩れていく過程」がなければ、今の英語の柔軟性や国際性はなかったかもしれない。

正しさばっかり追いかけてたら、言葉なんてとっくに息してないと思うんだよね。
ゴチャゴチャしてて、ちょっとヘンで、でもその“ヘン”が次のスタンダードになる。
言語ってさ、案外「いい加減」くらいがちょうどいいのかもしれないね。
崩れる言語、崩せない社会──“標準語”という制度の逆説
ここまで見てきたように、言語は本質的に変化し続けるものであり、
不規則性や曖昧さもまた、その進化の一部である。
だが一方で、近代以降の社会は言語に“秩序”を求めてきた。
「正しい言葉」と「正しくない言葉」を区別し、教育、メディア、法制度などを通じて“標準語”を制度化してきたのだ。
これは一見、合理的に見える。
しかし実際には、言語の自然な変化を抑圧し、しばしば言語の持つ多様性や柔軟性を損なってきた側面もある。
「言語を固定する」とはどういうことか?
言語が書き言葉として定着し、教育制度が整備されるにつれ、“正しい文法”“正しい綴り”“正しい発音”が教育的・政治的に定義されるようになった。
これは国家運営や識字率向上には効果的だったが、それに伴い、地方の方言、スラング、マイノリティの言語使用が「誤用」とされてきた。
つまり、「標準語」という制度は、言語の自然な“揺れ”や“変化”を押しとどめるブレーキでもある。
教育が“進化”を止める?
たとえば学校教育では、「見れる」「食べれる」「知らなかったんだよね」などの口語表現が訂正される。
これは規範としては理解できるが、実際にはそうした表現が話し言葉の自然な進化である場合も多い。
にもかかわらず、それを“誤り”と断定する構造が、変化の芽を摘んでしまうことがある。
崩れてこそ広がる、という逆説
皮肉なことに、英語が国際語として広がったのは、崩れやすかったからかもしれない。
- 文法の簡略化
- 発音の多様性
- 意味の柔軟さ(単語ごとの意味幅の広さ)
こうした“いい加減さ”があったからこそ、英語は非ネイティブにも取り込みやすくなり、結果として世界中で使われるようになった。
言語が“完成”していたら、そのまま広がる余地はなかったかもしれない。

崩れるって言うと、なんかネガティブに聞こえるけど、
むしろ「変われるかどうか」が、言葉の強ささなんじゃないかな。
ピシッとしてるだけの言葉より、グラグラしてても生き残れる言葉のほうが、ボクは好きだな。
シリーズ:言語はなぜ崩れるのか?
- 自然言語はなぜ崩れるのか?
- なぜ発音とスペルはズレていくのか?──英語とフランス語の“不一致”を解剖する
- 今読んだ記事→ 言語は崩れるほうが強い?──不規則性が生む柔軟性と多様性
- 言葉は誰のものでもある──共通語とマイノリティのせめぎあい
- 言語はなぜ崩れるのか?──まとめ
- 正しさは誰が決める?──言語規範と“誤用”という幻想


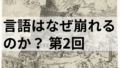
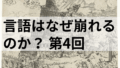
コメント