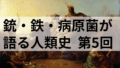巷では反グローバリズム、ナショナリズム回帰がしきりに取り沙汰されている。
自由貿易の揺り戻し、移民政策への反発、国境やアイデンティティを守ろうとする声――どれも今の世界を象徴する動きだ。
それは秩序を取り戻すための正しい反応なのか。それとも、制度が崩壊する前に人々が声を荒らげる終焉間際の熱狂にすぎないのか。
果たして滅ぶのはグローバリズムか、ナショナリズムか。あるいは二つの力を均衡させる新しい秩序なのか。
既存の制度が崩壊する前には熱狂が訪れる
歴史を振り返れば、制度が崩れ去る直前に、人々はしばしば熱狂に包まれる。
明治維新後の士族反乱や、南北戦争後に生まれたKKK。いずれも、旧制度を支えてきた人々が、自らの基盤を失う直前に見せた、最後の抵抗だった。
制度が揺らぐとき、その受益者たちは声を荒げ、最後の熱狂を見せるのだ。
こうした構造は、宗教の世界にも現れている。
中世末期のヨーロッパでは、教会の権威が揺らぎ宗教改革が進む中、既存の秩序を守ろうとする人々が原理主義的に過激化した。
異端審問や魔女狩りの熱狂は、キリスト教的世界観が崩壊しかけていたことの裏返しだった。
同じように、近代化・民主化の圧力にさらされたイスラム世界では、世俗化や民主化に抗う形で原理主義運動が台頭した。
制度の基盤が危機に陥るとき、人々は信仰や共同体の名のもとに過激さを増し、それを「正義」と信じて立ち上がる。
崩れ始めた『先進国の国民』の優位性
グローバリズムは、止めようのない流れであると私は考える。
技術の進歩と資本の流動化、情報網の拡張──それらは人類が選んだというより、文明が自然に辿りついた帰結に近い。
問題はその流れそのものではない。
問題は、その流れの中で静かに崩れつつある優位のほうにある。
かつて、先進国に生まれるということは、それだけで人生のある程度を約束されたようなものだった。
同じ労働でも先進国に生まれただけで発展途上国の国民よらもはるかに高い賃金を得ることが可能であった。
それが、グローバリズムによって音を立てて崩れ始めている。
通信と物流が国境を越え、仕事が移転し、賃金水準が均されていく。
「先進国に生まれた」というだけのカードは、もはやかつてほど強力なものではなくなった。
かつては生まれた国の豊かさが、努力や才能を超えて人生の行方を決めていた。
だが今は、情報化やテクノロジーの発達により国家間の格差は急速に縮まりつつある。
たとえばかつてはどれほど優秀でも東南アジア途上国の国民が日本のアルバイトの賃金を超えることはほとんどなかった。
しかし今では、能力次第で日本人より高い収入を得ることも珍しくない。
つまり、かつて越えられなかった生まれた国ごとのカードの格差を、個人の能力で乗り越えることが容易になったのだ。
これは人類全体で見れば喜ばしい変化である。
だが、その裏で崩れているのが、先進国カードの優位性である。
かつて当たり前とされた生活水準や雇用の安定は、もはや国籍によって保証されるものではなくなった。
優位を失った社会が向かう先
グローバリズムがもたらしたのは、単なる経済の変化ではない。
それは「生まれた国というカード」の崩壊であり、長く信じられてきた先進国民という物語の終わりでもある。
国境の外に押し広げられた競争の中で、先進国の中間層は自らの優位を失い、その不安と反発がナショナリズムとして噴き出している。
イギリスでも同じ現象が見られる。
ロンドンで働く友人によれば、現場労働の分野では最も信頼できるのはイギリス人よりも移民労働者だという。
彼らは長時間働き、与えられた責任を果たす。
一方で、同じ職場のイギリス人は、勤勉さよりも待遇への不満を口にすることが多い。
しかしそれは「国民性」の問題ではない。
本来、こうした職種は社会的評価が低く、賃金水準も抑えられがちなため、長く高度な人材が定着しにくい領域だった。
対して、移民労働者は一定の教育や能力を持ちながら、移民先では言語や制度の壁によって単純労働にしか就けない人々である。
つまり、彼らは必ずしも能力的に低いわけではない。
彼らの勤勉さが際立つのは、先進国の内部で「国籍カードの優位性」が崩れた結果、労働の序列が入れ替わったからである。
生まれただけで守られていた構造が崩れるとき、人はその不安を外にぶつける。
イギリスのEU離脱(ブレグジット)は、まさにその心理の噴出だった。
熱狂は誰のものか──反発の正体
グローバリズムによって、「移民=単純労働者」という構図はすでに崩れつつある。
今や、能力やスキル次第で所得が決まり、国籍カードの優位は相対的に弱まった。
その結果、かつて「先進国に生まれた」というだけで享受できた優位が失われつつあり、
その喪失感が、欧米や日本をはじめとした先進国でナショナリズムを再燃させている。
だが、ここに見られる熱狂は、世界全体から見れば一種の防衛反応でもある。
国家間の格差が縮まり、発展途上国が豊かになっていくことは、本来は人類にとって望ましい変化だ。
それにもかかわらず、先進国の一部の層が「自国の優位を守れ」と叫ぶのは、制度が変わるときに生じる過渡期の反発にほかならない。
反グローバリズムや排外主義の動きは、決して「歴史の修正」ではなく、「特権の終焉に対する抵抗」なのだ。
この意味で、保守の一部が語るように
「ナショナリズムの復活こそが正しい流れだ」という論調は、歴史的にも、構造的にもフェアではない。
熱狂は必ずしも再生を意味しない。
制度が崩壊する直前にも、人々はしばしば声を荒げる。
では今の時代の熱狂は、再生の兆しか、終焉の前触れか。
──死ぬのはグローバリズムか、ナショナリズムか。
〈追記〉
この記事の執筆中、速報で高市早苗が日本の総理大臣に就任したという報が入った。
いま世界各地で進むナショナリズム回帰の流れの中で、この出来事もまたひとつの時代の空気を映しているように思う。
偶然かもしれないが、「制度が揺らぐとき、人々は声を荒げる」という本稿のテーマを裏づける象徴的な出来事として記録しておきたい。