なぜある文明は他者を征服し、ある文明は支配される側に回ったのか。
人類の歴史を貫くこの問いに対し、ジャレド・ダイアモンドの『銃・病原菌・鉄』は、人種や民族の能力差ではなく「環境と地理」という要因から答えを導いた。
本書は、私にとって考え方を大きく変えるきっかけとなった一冊である。文明の格差を「必然の帰結」として描きつつも、その視点はむしろ希望を与えてくれる。今回は、その核心に迫ってみたい。
環境が文明の運命を分けた
人類の歴史を見渡すと、ある文明は征服者となり、ある文明は支配される側に回ってきた。なぜこうした「格差」が生まれたのか。この問いに対して、長らく「人種の優劣」や「文化の力」といった説明がなされてきたが、それでは十分に答えにならない。
ジャレド・ダイアモンドの『銃・病原菌・鉄』が提示したのは、人類史を決定づけたのは能力の差ではなく「環境の差」だったという視点である。ヨーロッパ人がインカ帝国を征服できたのは、銃や鉄といった技術を手にしていたからであり、さらに彼らが持ち込んだ病原菌が先住民を壊滅させたからだ。しかし、その背景にあるのは、ヨーロッパ人が特別に優秀だったからではない。
ヨーロッパには、栽培に適した穀物や家畜化しやすい動物が多く存在していた。ユーラシア大陸は東西に広がり、同じ緯度帯で作物や技術が伝播しやすい。こうした地理的・生態的条件が、ヨーロッパに有利な「スタート地点」を与えたにすぎない。
私はこの視点に強く納得した。というのも、文明の優劣を「民族の資質」で説明する言説を無意識に受け入れていた自分がいたからだ。『銃・病原菌・鉄』は、そうした思い込みを根底から揺さぶり、歴史をもっと大きな枠組みで見る必要があると気づかせてくれた。人類史における文明の差は、努力や能力以前に与えられた環境の条件によって大きく方向づけられていた──それは、決して直感的ではないが、納得せざるを得ない説明だった。
ただし、同じユーラシア大陸に属し、同じように環境の条件を持ちながらも、近代以降の歴史では明確な分岐が生まれた。すなわち、産業革命を先行させたヨーロッパと、それに出遅れたアジアである。環境要因が文明格差をつくったことは確かだが、そこからさらに「なぜヨーロッパだったのか」という問いが立ち上がる。
この点を考えると、地理や資源だけでは説明しきれない「国家間競争」や「体制のあり方」といった要素が浮かび上がってくる。以後の章では、この「偶然と必然」「地理と制度の交錯」をさらに掘り下げていきたい。
偶然と必然のあいだにある病原菌
ヨーロッパ人がアメリカ大陸に上陸したとき、最大の「武器」となったのは銃でも鉄でもなく、病原菌だった。天然痘やインフルエンザといった病気は、ヨーロッパ人が長い年月をかけて家畜との共生のなかで耐性を獲得してきたものである。しかし、牛や豚、馬といった家畜をほとんど持たなかったアメリカ大陸の人々にとって、それは未知の脅威だった。
16世紀のスペイン人征服者ピサロがインカ帝国に進軍したとき、天然痘はすでに帝国内に蔓延しており、皇帝アタワルパの即位をめぐる混乱も、この疫病による人口激減と王位継承危機が背景にあったとされる。つまり、スペイン人の鉄砲や戦術だけでは到底覆せないはずの「大帝国の体制そのもの」が、病原菌の襲来によって内部から弱体化していたのだ。
ここには確かに「偶然」の要素がある。もしユーラシア大陸に多様な家畜が存在しなければ、ヨーロッパ人は病原菌への耐性を獲得できなかっただろう。しかし一方で、これは単なる偶然の産物ではない。ユーラシア大陸の広大さと東西方向の地理的な広がり、家畜化可能な動物が集中して存在した環境、そして人と動物が密接に暮らす生活様式──こうした条件がそろっていたからこそ、ヨーロッパは「病原菌を味方につける文明」になったのである。
つまり、病原菌の猛威は偶然のように見えて、地理的・環境的な積み重ねが必然を形づくっていた。
私はこの視点に強く共感する。歴史の分岐は誰かの意志ではなく、環境が生み出した条件の中で「偶然」が重なり、その偶然がやがて「必然」へと変わっていく。
そしてこの論理は、近代以降の歴史──特に産業革命の起点をめぐる議論にもつながっていく。同じユーラシア大陸にありながら、ヨーロッパは技術革新を先行させ、アジアは出遅れた。その背景にもまた、「環境が偶然を必然に変える構造」が潜んでいるのではないか。次章では、その分岐の意味を考えてみたい。
ユーラシア大陸の東西分岐
同じユーラシア大陸にありながら、近代の歴史はヨーロッパとアジアで大きな分岐を見せた。特に鮮明なのが、ヨーロッパで産業革命が先行し、中国をはじめとするアジアが後れを取った理由である。
その差を理解するには、単なる地理的条件だけでなく、政治体制と競争構造を見なければならない。
ヨーロッパは地理的に統一されにくく、多くの国家がせめぎ合う状況が長く続いた。外敵の圧力や隣国との競争が常態化し、各国は「国力を増すための合理的選択」を迫られる。軍事技術の革新、経済制度の工夫、交易の拡大──すべてが生き残りの条件であった。その競争環境が、結果的に産業革命への加速装置となった。
対照的に、中国は地形的に統一しやすく、長期にわたって大帝国が維持されてきた。外敵がいないわけではないが、内政を安定させることの方が優先され、技術や制度の革新は「体制を維持するための範囲」に収まった。富国強兵ではなく、秩序の持続が重視されたのである。そのため、潜在的な技術や経済力があっても、イノベーションを社会全体に波及させる仕組みにはつながりにくかった。
日本を見ても、この構図は当てはまる。戦国時代には国が分断され、各地の大名が競い合った結果、鉄砲の大量生産や経済体制の整備が急速に進んだ。ところが江戸時代に入ると、平和が長期化し、外敵の脅威もほとんどなくなった。その結果、技術の進化は「生活の安定」を支える方向には発達したが、産業革命につながるような革新は停滞した。
こうして見ると、ヨーロッパが産業革命に至ったのは偶然ではなく、「国家間競争が合理的選択を迫り続けた必然の帰結」だったと言える。逆に言えば、外敵が少なく、体制の安定を優先する社会では、技術や制度の飛躍は必ずしも必要とされなかったのだ。
この視点は、「環境が偶然を必然に変える」という前章の論理とつながる。地理的条件が「国家の分断」を生み、それが競争と革新の必然を導いたのである。次章では、こうした分岐の中で決定的な役割を果たした「病原菌の衝撃」について改めて掘り下げてみたい。
現代への示唆
『銃・病原菌・鉄』が示したのは、文明の優劣を「人種の能力」で説明するのではなく、環境の条件が歴史を大きく方向づけたという冷徹な構造である。偶然の積み重ねが必然となり、文明の格差を生み出した──その視点は、歴史を民族や国家の特性から語る従来の思考を大きく揺さぶるものだった。
私はこの本から「希望」を感じた。人種や民族に優劣を見出す必要はなく、歴史の差異は与えられた環境に由来する。もしそうならば、未来を決めるのは「どの環境をつくり出すか」「どんな制度を築くか」という人間の選択にかかっているからだ。
もちろん、国家や民族というフィクションは人類史において大きな役割を果たしてきた。だが同時に、そのフィクションはしばしば格差や戦争を正当化してきた。その物語を乗り越える理性が、これからの時代には必要になる。
『銃・病原菌・鉄』を読むことは、過去を理解するだけではない。偶然と必然の交錯を見抜き、未来をどう設計するかを考えるための出発点でもあるのだ。

ユーラシアで人類が本格的に家畜化に成功したのは、馬・牛・豚・羊・ヤギといった限られた種類だけ。インカ帝国にはアルパカやリャマがいたけれど、荷役や毛皮用が主で、農業や戦争を変える「力」にはならなかったんだ。



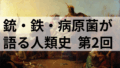
コメント