私たちは日常的に、職場でも学校でも人を「苗字」で呼ぶことに違和感を感じない。けれど、時代劇では「〇〇殿」「〇〇さま」と下の名前で呼ぶ場面が目立つ。実は日本も、かつては名前呼びが当たり前だった国だった。なぜ苗字がこれほど一般化したのか? それは自然な文化ではなく、近代国家によって制度的に「設計された」呼称文化だった――。
この記事では、日本における苗字呼びの定着の歴史と、その背景にある軍隊や学校制度の影響、さらに世界各国との比較を通して、呼び方が映し出す社会の姿を探る。
江戸時代まで:名前呼びが当たり前だった日本
現代の日本では、ビジネスシーンでも学校でも、苗字で呼び合うのが当たり前だ。だが江戸時代まで遡ると、人を苗字で呼ぶ習慣はむしろほとんど存在しなかった。なぜなら、当時の社会では苗字は「家」の名であり、「個人」を指す呼称には使われていなかったからである。
武士の場合、フルネームは「姓+諱(いみな=下の名前)」で構成されていたが、実際の会話では「諱」や「通称(仮名)」で呼ぶのが通例だった。たとえば「伊達政宗」は「政宗さま」、「織田信長」は「信長公」といった具合である。苗字は記録や儀礼の場面では重要でも、日常の呼びかけでは用いられなかった。苗字で直接呼ぶのは、かえってよそよそしいか、不敬とさえ見なされることがあった。
庶民の場合はさらに制限があった。そもそも江戸幕府は、農民や町人が公に苗字を名乗ることを禁じていた(名乗っても「非公式」扱い)。そのため、庶民同士は「屋号」「職業名+名前」「下の名前+さん」などで呼び合っていた。
たとえば「魚屋の甚兵衛さん」「大工の清吉」といった呼び方が典型である。これは、相手が属する職業や商売、地域などの属性に加えて、個人の名前を重ねることで「その人らしさ」を表現する文化だったとも言える。
つまり、江戸時代までの日本社会では、苗字はあくまで「家格」や「由緒」を示す記号であり、個人の呼び名としてはふさわしくなかったのだ。

「才谷梅太郎」は坂本龍馬の変名だけど、これは当時の通称文化の一部で、身分や目的に応じて名前を使い分けてたんだ。
今で言えば、ペンネームを名刺に書いてるような感覚に近いかもしれないね。
それでは幕末は?
現代の私たちは、幕末の人物を「坂本龍馬」「西郷隆盛」「勝海舟」と、つい苗字で呼んでしまう。けれど、実際の会話の中では、本当にそう呼ばれていたのだろうか?
どうやら、当時の人びとは下の名前に敬称をつけて呼ぶのが一般的だったようだ。「龍馬どの」「利通さま」「海舟先生」──こうした呼び方のほうが、現実にはなじんでいたはずである。
たとえば、勝海舟の書簡には「坂本」という表記が見られるが、これはあくまで文書上での記述に過ぎない。勝と龍馬は明確な上下関係のある親密な間柄だったことから、実際の会話では「龍馬」または「龍馬さん」と呼んでいた可能性が高いとされる。つまり、書き言葉=苗字、話し言葉=名前という棲み分けがあったのだ。
では、なぜ私たちは「苗字で呼んでいた」と思ってしまうのか?
その背景には、後世に作られた時代劇や歴史小説、教科書などが、人物名を「苗字+名前」や「苗字単独」で語ってきたことがある。記録として整っている一方で、会話の温度感までは再現されない。
映像作品などでは、「坂本!」「西郷どん!」という呼び方が使われることもあるが、それは現代の観客が人物を識別しやすいようにした演出上の工夫であって、必ずしも当時のリアリティを反映しているわけではない。
つまり、私たちが「幕末の人たちも苗字で呼び合っていた」と思ってしまうのは、実際の歴史というより、後世の“語り方”に引っぱられた記憶なのかもしれない。
明治維新と苗字の「制度化」
江戸時代には特権階級の象徴だった苗字が、明治時代になると一転、すべての人に義務化された。
それを決定づけたのが、1875年(明治8年)に発令された「平民苗字必称令」である。
これにより、身分制度の枠組みを超えて、すべての国民が「公的に苗字を名乗る」ことが義務づけられた。
背景には、近代国家の建設に不可欠な「個人管理」の必要性があった。徴兵制、地租改正、学籍管理、戸籍法──いずれも個人を一意に特定しなければ成立しない制度であり、苗字はそのための“国民番号”としての機能を果たすことになる。
重要なのは、ここで定められた苗字が、あくまで「国家の管理都合によって付与・選定されたもの」だったことだ。
庶民の中には、自分の村の名前、屋号、尊敬する人物の姓などを参考に「自作の苗字」を申請した者もいた。
逆に、役所から適当に与えられた苗字をそのまま受け入れるしかなかった人も多く、明治初期は「苗字の混乱期」でもあった。
こうして苗字は、それまでの「家の格や出自を表す象徴」から、「個人識別のための番号」へと大きく意味を変えていく。
これは、日本における苗字文化の転換点であり、苗字が日常的に使われる土台が制度として整えられた瞬間だった。
なぜ日常にまで定着したのか?
1875年の平民苗字必称令によって、すべての人が苗字を名乗るようになった。
しかしそれだけでは、「苗字で呼ぶ文化」が日常にまで広がったとは言えない。
名前呼びが根強く残っていた庶民社会に、苗字呼びが本格的に浸透していくには、それを“当たり前”とする空間が必要だった。
その空間こそが、軍隊と学校である。
徴兵制によって整備された明治政府の軍隊では、階級と苗字で呼び合うのが基本となった。
「田中一等兵」「佐藤中尉」──このような呼び方は、個人を役割と階級で管理するための、機能的かつ合理的な呼称体系だった。
兵士が同姓同名になることも多いため、フルネームではなく「苗字+階級」が最適だったのだ。
同様に、学校でも教員が生徒を苗字で呼ぶスタイルが定着した。
名簿は苗字順に並べられ、教師は「鈴木くん」「高橋さん」と苗字で呼び、成績表や出席簿にも苗字が用いられた。
これは軍隊と同じく、個人を組織内で識別・評価する単位としての苗字使用であり、やがて教師・生徒間だけでなく、生徒同士でも苗字呼びが広がっていった。
こうして、「苗字で呼ばれること」が、組織的に“当たり前”の経験として刷り込まれ、それが家族や地域社会などにも逆流する形で広がっていった。
とくに戦後の高度経済成長期には、会社が人間関係の中心となり、苗字呼びは職場の礼儀・常識として完全に定着していった。

軍隊・学校から始まる苗字呼び文化
明治以降の日本では、国家の中枢をなす制度(軍・学校・役所)がいずれも「苗字+階級・敬称」で呼ぶ形式を採用した。これは近代国家の管理効率を追求する機構的判断であり、命令系統の明示や記録整理においても合理的だった。結果として、そこに属した人々が「苗字で呼ぶのが当たり前」という感覚を持ち帰り、社会全体に拡散していったんだ。
世界の呼び方文化と比較する
日本では「苗字で呼ぶ」ことが社会の基本ルールになっているが、それは決して世界共通の感覚ではない。むしろ、「名前で呼ぶ」ことが自然とされている文化圏の方が少なくない。ここではいくつかの代表的な国や地域を取り上げ、日本の苗字文化と比較してみよう。
ヨーロッパ:公式の場では苗字、親しい関係では名前
多くのヨーロッパ諸国では、公的・職務的な場面では苗字で呼ぶのが標準である。
たとえばドイツでは「Herr Müller(ミュラー氏)」、フランスでは「Monsieur Dupont(デュポン氏)」という具合に、敬称+苗字が基本形となる。
一方で、プライベートでは名前呼びに切り替わることが多い。友人や家族、恋人同士はファーストネームで呼び合い、公私の切り替えによって呼び方も変化するのが特徴だ。
アメリカ:ファーストネーム文化の代表格
アメリカでは、職場でも上司を「ジョン」「エリック」と下の名前で呼ぶのが一般的。
この文化は、アメリカが「平等主義」と「個人主義」を理念として建国されたことと深く関係している。
苗字には民族的・出自的な意味が強く込められるため、あえてファーストネームでフラットな関係性を演出する文化が発達した。
ただし、軍隊や官僚組織、病院などの制度的空間では、階級や肩書きとセットで苗字が使われる(例:”Private Smith”, “Dr. Johnson”)。
アジア:儒教文化圏は苗字重視、東南アジアは名前重視
日本と同様に、韓国や中国といった儒教文化圏では、苗字で呼ぶのが基本。
とくに韓国では、名前呼びは親密な関係に限られ、苗字+職業や敬称での呼びかけが社会常識になっている。
一方でタイやベトナム、インドネシアなど東南アジア諸国では、下の名前で呼ぶ文化が主流であり、苗字はあまり使われないか、使用頻度が低い。タイでは法的に苗字を持っていても、日常的にはファーストネーム+敬称(例:「Khun Somchai」)が用いられる。
アフリカ:民族・言語・植民地支配の影響で多様
アフリカ諸国は非常に多様だが、植民地支配を受けた地域ではヨーロッパ式の苗字呼びが導入されたケースが多い。
ただし、伝統社会では「名前+父の名」「名前+役割」など、家名よりも所属・関係性を重視した呼称が一般的だった。
たとえばエチオピアでは「苗字」の制度がなく、個人名+父の名前を公式文書で用いる。
また、イスラム文化圏では「〜の息子」(bin〜)の形式で父称を入れる命名法があり、苗字という概念とは異なる。
なぜアメリカでは苗字呼びが定着しなかったのか?
日本では、学校・職場・役所とあらゆる場面で「苗字で呼ぶ」ことが社会常識となっている。だが、アメリカではまったく逆だ。ビジネスの場であっても、上司を「ジョン」、顧客を「サラ」と、ファーストネームで呼ぶのが基本。むしろ苗字で呼ぶと、どこか距離を感じさせたり、古風な印象を与えたりする。
これは単なる文化の違いではなく、アメリカという国の成立と理念そのものが深く関係している。
平等主義と反階級主義が前提
アメリカは、王や貴族のいない「自由で平等な国家」として建国された。
ヨーロッパのような身分制度に強く反発し、肩書きや家柄によらない対等な呼び合い方=ファーストネーム文化が定着した。
このため、苗字はむしろ「出自・階級・ルーツ」を思わせるものとして、敬遠されることすらある。
代わりに、名前で呼び合うことが、相手を一人の人格として尊重するサインとみなされるのだ。
多民族国家ゆえの「名前重視」
アメリカは、様々な民族・宗教・文化が混在する移民国家である。
苗字には、「どこの国の出身か」「どんな宗教か」といった出自情報が強く現れてしまう(例:Goldberg、Nguyen、Kowalskiなど)。
そこで、個人の背景を問わない名前呼びが、無用な差別や先入観を避ける手段としても機能するようになった。
それは単なる習慣ではなく、個人主義と多様性を支える社会的ツールでもある。
苗字呼びは「例外的な制度空間」にとどまる
もちろん、アメリカでも苗字がまったく使われないわけではない。
軍隊や警察、官僚機構、医療機関など、秩序や階級、肩書きが重視される空間では「苗字+敬称/役職」が今でも基本だ。
しかしそのような呼び方は、あくまで例外的・公式な文脈に限られており、日常生活にまで広がることはなかった。
イギリスとの違い──なぜアメリカは名前呼びを選んだのか
アメリカはイギリス文化圏に生まれた国だが、呼称文化においては真逆の道を歩んでいる。
イギリスでは今でも「Mr. Smith」「Miss Johnson」といった苗字+敬称の形式が標準的で、階級社会の名残が強く残っている。職場でもフォーマルな文脈では苗字呼びが基本であり、「下の名前で呼ぶ」のは親密な間柄に限られる。
一方、アメリカでは建国時からこうした形式や身分的呼称を否定し、「ジョン」「サラ」とファーストネームで呼び合う文化が徹底された。これは単なる習慣ではなく、社会の在り方そのものに対する態度の違いである。
近年のイギリスでは若者文化やフラットな職場関係の広がりとともに、ファーストネーム呼びも徐々に広まりつつあるが、苗字+敬称の形式は今なお“格式”として根強く残っている。
アメリカとイギリス――同じ英語圏にして、呼び名から見える社会構造はまるで異なるのだ。
名前か苗字か──それは文化か、制度か
日本では、人を苗字で呼ぶのが当たり前とされている。職場でも学校でも、苗字に「さん」「くん」をつけるのが礼儀であり、相手に対する基本的な距離の取り方になっている。だが、この呼び方が自然に育まれた文化かと言えば、決してそうではない。
むしろ、明治期に国家が制度的に苗字を強制し、学校や軍隊などを通じて「当たり前のもの」に作り変えていった結果である。
つまり、日本の苗字呼びは“文化”というより“制度が作った習慣”だ。
一方で、アメリカのように「下の名前で呼び合う文化」が守られてきた国もある。こちらは制度によって強化されたものではなく、建国の理念や社会の価値観から自然に根付いた文化だ。
イギリスのように、制度的には苗字呼びを維持しつつ、若い世代ではファーストネームが広まりつつある国もある。つまり、どちらが「正しい」ではなく、何を社会が重視してきたかで呼び方も変わるのだ。
呼び方に映る社会のかたち
呼び方ひとつには、その社会が重んじる価値観がにじみ出る。
- 苗字で呼ぶ社会は、秩序や制度、役割と距離感を大切にする。
- 名前で呼ぶ社会は、平等や個人、親しみと接近を重視する。
そして日本の場合、それは「伝統だから」ではなく、「制度がそう定めたから」始まったのだ。
呼称と身分制──日本とイギリス、ふたつの階級社会
「階級社会=苗字呼び」というイメージは根強い。だが、これはすべての国に当てはまるわけではない。
たとえば、江戸時代の日本もれっきとした身分社会だったが、武士たちは互いを苗字で呼ばず、下の名前に「さま」「どの」などをつけて呼び合っていた。織田信長は「信長さま」、伊達政宗は「政宗どの」──家名よりも“個”に敬意を払う呼称が主流だった。
一方、イギリスの貴族社会では「ミスター・スミス」「レディ・チャタレー」など、苗字に敬称や爵位を組み合わせる形式が基本だった。苗字そのものが「家格」や「領地」を象徴し、個人ではなく“家”を尊重する姿勢が色濃い。
同じように階級意識の強い社会でも、呼称が何を指すのか──“個人”なのか“家系”なのか──には大きな違いがある。
これは、呼び方というより、「人間関係の起点をどこに置くか」という文化的な問いでもあるのだ。
おわりに
私たちが誰かをどう呼ぶかは、単なる言語習慣ではなく、その社会が人間関係をどう設計してきたかの反映である。
苗字で呼ぶ国も、名前で呼ぶ国も、その背後には制度と文化の交錯がある。
そして今、グローバルな交流が進む中で、日本の呼称文化も変化の時を迎えているのかもしれない。
呼び方は時に、社会そのもののかたちを映し出す鏡となる。
何気ない「〇〇さん」という呼びかけの中に、あなたの属する社会の価値観が、静かに潜んでいるのかもしれない。


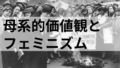

コメント