帝国はなぜ「搾取するほど損をする」構造に陥ったのか
帝国は、利益のために領土を拡げた。だがその拡張がやがて本国の足を引っ張る負債と化す。
これは感情論でも倫理の問題でもない。純粋な損得の話である。
イギリスにとってのインド、フランスにとってのインドシナ、日本にとっての満州。
いずれも「利益の源泉」として支配されたが、その維持には軍備、行政、監視、補給といった継続的コストがのしかかっていた。
最初は“割に合う”ように見えても、時間とともに「搾取モデル」は赤字経営に転じる。
搾取モデルの崩壊──「五段階の死」
帝国的支配がもたらす構造的限界は、以下の五段階で理解できる。
- 育てずに奪う──教育・産業を抑制し、原料と労働だけを抽出する
- 反感が高まる──文化的抑圧・経済的格差により反乱と独立運動が噴出
- 維持コストの増大──軍事・行政・インフラ維持の負担が本国を圧迫
- 国際的非難と孤立──「民族自決」「人権」の原則が世界的規範に
- 支配より協調のほうが得になる──合理性が完全に崩れる
その最終段階で帝国は、自らの手で「帝国であること」を放棄するしかなくなる。
供給は増えても需要は育たない──市場殺しの支配構造
搾取モデルの最大の欠陥は、市場を育てないことだ。
原料や労働力の「供給」は確保できても、住民は低賃金と低教育に閉じ込められ、消費者にならない。
つまり、帝国は**“自分の製品を買ってくれる中間層”を意図的に生まれさせない。**
その結果、植民地は市場としても不完全で、本国の生産は過剰に。
この構造が、1929年の世界恐慌の背景にもつながっていく。
小日本主義──理想ではなく冷徹なリアリズム
この非効率を見抜いたのが、戦前の自由主義者・石橋湛山である。
湛山は、「朝鮮も台湾も放棄すべきだ」と主張した。
彼は決して理想論者ではなかった。
むしろ、「コストに見合わない植民地は、手放した方が得だ」というリアリストだった。
帝国の維持に必要な巨額の予算、対日感情の悪化、市場としての信頼の喪失──
それらをすべて勘案し、湛山は「信頼を築いて市場として成長させた方が、自国の利益になる」と喝破した。
独立させた方が“儲かる”という逆説
第二次世界大戦後、多くの帝国は植民地を失った。
だがそれによって“損をした”とは限らない。
- アメリカは、日本やドイツという“かつての敵”を最大の経済パートナーにした
- イギリスは、英連邦を通じて緩やかな文化経済圏を維持した
- 日本も、アジアの独立国と経済協力を進めていった
これは、支配より信頼、搾取より共栄のほうがリターンが大きいことを示している。
経済はプラスサムである──それでも人はゼロサムで考える
それでもなお、多くの国民や政治家は、「支配を手放す=損失」と感じた。
なぜか?
それは、人間が本能的に**「経済はゼロサムゲーム」だと誤解しやすい**からである。
「他国が得をする」ということが、「自国が損をしている」かのように感じられる。
しかし現実の経済は、**プラスサム(共に豊かになれる構造)**であり、
支配の解除=新たな市場の誕生=信頼の構築=長期利益の増加、につながる。

湛山の提案が受け入れられなかったのは、「損をして得を取る」戦略が、大衆心理とナショナリズムには響かなかったからなんだ。
支配から共栄へ──歴史が教えるもう一つの合理性
帝国は「奪うことで拡張」しようとした。
だが、**「与えなければ持続できず」「信頼されなければ利益を得られない」**という構造が、次第に明らかになっていった。
石橋湛山が見抜いたのは、道徳ではない。経済の構造的限界である。
そしてその洞察は、21世紀のグローバル経済でもなお通用する。

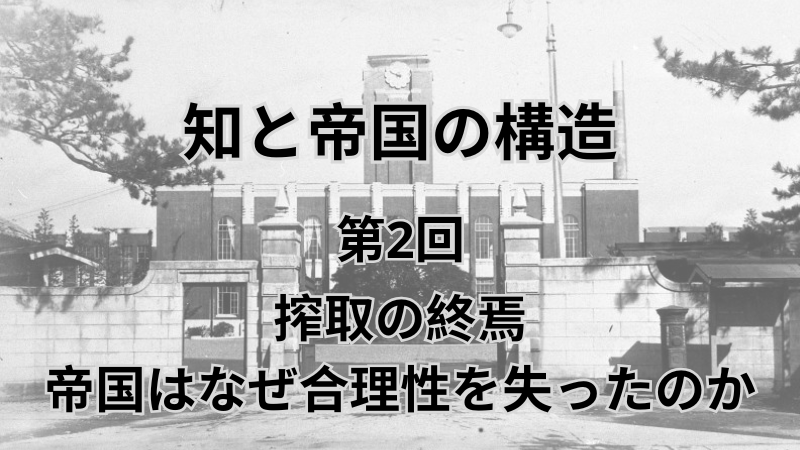
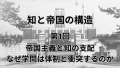
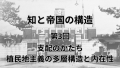
コメント