現代において、「帝国」という言葉は過去の遺物のように響く。
だが果たして、帝国主義は本当に終わったのだろうか?
このシリーズでは、帝国とは単なる軍事力や領土支配ではなく、
知の正当化、経済の合理性、そして内在する支配構造の三層で成り立つ複雑なシステムだったことを掘り下げていく。
- なぜ学問は、しばしば体制にとって「都合の悪い存在」になるのか?
- なぜリベラリズムは、帝国と衝突し、やがて消費されていくのか?
- なぜ経済合理性から見ても、植民地支配は破綻していたのか?
- そしてなぜ、国家は今も「自国の中の他者」を生み出し続けるのか?
帝国は滅んでも、その論理は今も残っている。
知をめぐる支配の地図を、いま一度、塗り替えてみよう。
帝国は「力」だけでなく「正しさ」で支配する
帝国は銃と軍艦で支配したわけではない。
少なくともそれだけではない。
国家が外部を征服し、内部を統治しようとするとき、常に必要とされるのは「正当化」の装置だ。
それが宗教であることもあれば、文明の優位であることもあった。
近代以降、それを担ったのが「学問」である。
民族の優劣を示す人類学、統治正当性を示す法学、社会の進化段階を示す歴史学や政治思想。
こうした「知」はしばしば帝国主義と手を取り合い、支配の知的裏付けとして機能してきた。
植民地主義を支えた学術構造──人種学・東洋学・法制史
19世紀、ヨーロッパ列強は学術の名の下に植民地を「測定」し、「分類」し、「改良の対象」として位置づけた。
- フランスの東洋学(Orientalisme)はアラブ・イスラム世界を“研究”しながら、支配の理論を組み上げた。
- イギリスの人類学は、「未開民族」と「文明人」を区別し、宗主国の支配を自然なものと見せかけた。
- インドでは英国統治に都合の良い形で「伝統法」が再構成され、「植民地法制」として整備された。
これらは単なる偏見ではなく、制度化された知識の形だった。
つまり、学問それ自体が支配の構造の中に組み込まれていたのである。
知はいつから体制の「敵」になったのか──知の二重性
だが重要なのは、知が常に体制に従属していたわけではない、という点である。
学問とは、構造的に「既存の前提を疑う場」であり、
たとえ支配の正当化に使われていたとしても、その内部から「本当に正しいのか?」と問い直す契機を生み出してしまう。
言い換えれば、知には二重性がある。
一方でそれは支配の正統性を支える装置であり、他方では、支配の内側から矛盾を告発する存在にもなりうる。
この二重性こそが、権威にとっての知の厄介さであり、そして現代における学問と権力の対立にも通じる構造である。
日本の大学における自由とその抑圧──滝川事件
この構造は日本にも当てはまる。
1933年の滝川事件──京都帝国大学の刑法学者・滝川幸辰が、自由主義的思想を理由に政府から休職処分を受けた事件は、
まさに「国家と学問の衝突」を象徴している。
滝川は社会の刑罰権を、国家の権威ではなく個人の尊厳に根ざした理性によって制御すべきとした。
だが、それは「天皇の国家」に反するとされた。
教授たちが抗議の辞職を申し出ても、政府は「学問の自由」ではなく「国家の道徳」を優先した。
この事件は、日本における知識人の孤立と、国家権力による学問の統制の始まりを示す警鐘であった。
アメリカ現代大学とトランプ政権──再来する知と体制の対立
2020年代、アメリカでは似たような構図が復活する。
ドナルド・トランプ政権は、大学に対して「反米的」「左翼的」「WOKEすぎる」として圧力をかけ、
知の場を“敵の温床”と見なす政策を展開した。
- DEI(多様性・公平性・包摂性)プログラムの廃止要求
- 「愛国教育」の義務化
- ハーバードやMITへの資金凍結
- 保守派学生による「言論の自由」訴訟支援
さらに、貿易政策においてもその構造は露わになった。
中国との対立を象徴した対中関税戦争は、表面的には経済政策だったが、実際には**「国家の敵を作り、国内の敵(大学)を巻き込む構図」**だった。
- 「中国がアメリカを搾取している」
- 「自国の繁栄を奪っている」
→ だから関税で戦う、大学はそれに反対する“売国の拠点”
このゼロサム的世界観こそ、トランプ政権が大学を警戒し、敵視した背景である。
知は、経済も政治もゼロサムではないと知っている。それが、体制の敵になる理由だ。
なぜアカデミズムはリベラルになるのか?その構造的理由
大学は意図してリベラルになるわけではない。
だがその構造自体が、リベラルな思考を生み出しやすい。
- 学問は「既存の前提を疑う」ことから始まる
- 国際的な共同研究は「ナショナリズム」と相性が悪い
- 多様性と平等を受け入れないと、知的議論が成立しない
さらに、経済は本質的にプラスサムであるという知見は、
「自国だけが得をすべき」と考えるゼロサム政治とは相容れない。
つまり、アカデミズムはその存在そのものが、体制のゼロサム幻想にとって異物なのだ。
「知識人」はいつも帝国の外側にいるのか?
すべての学問が正義の味方ではない。
かつての人種学や植民地法学がそうであったように、「体制に奉仕する知識」もまた存在する。
だが同時に、その中から「反省し、体制にノーを突きつける知」もまた現れる。
それが滝川であり、石橋湛山であり、戦後の知識人であった。
学問は、体制の外側に立つことによってしか、その誠実さを証明できない。
そしてその知は、時に国家よりも先に未来を見ている。

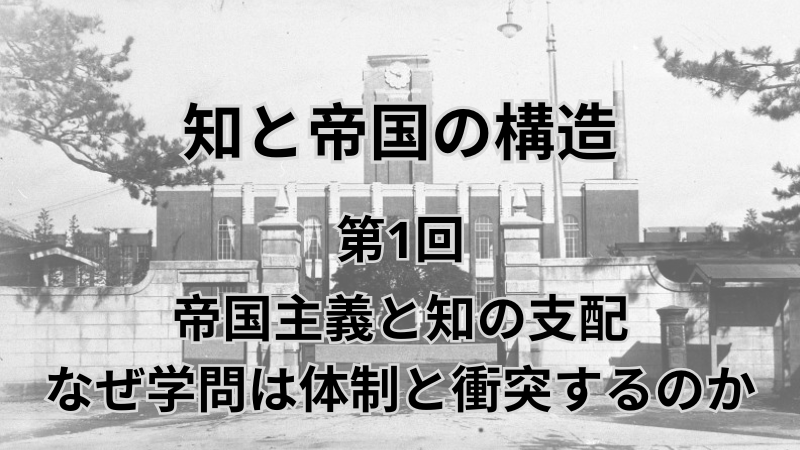

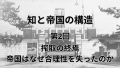
コメント