「国家がなければ、誰が国を守るのか?」
アナーキズム的な社会構想に対して、必ず投げかけられるこの問い。
確かに、国家なき社会は従来の“国防”という枠組みでは脆弱に見える。
だが、武力や防衛は、国家に独占されなければならないのだろうか?
本稿では、アナーキズムの視点から「武力と秩序」の関係を再考し、
クルド人自治区・ロジャヴァなどの実践例も交えながら、
“支配なき防衛”の可能性を探る。
国家=防衛の前提という常識
「国家がなければ、誰が国を守るのか?」
この問いは、アナーキズムやリバタリアニズムの思想に対する“決定打”のように投げかけられる。
それは、国家が存在しなければ、秩序も安全も維持できないという信念に基づいている。
たしかに、私たちは国家に守られて生きている。
国防、警察、外交、法律──すべてが国家という“見えない機関”を通じて機能している。
しかし、この「国家=守る側、国民=守られる側」という構図は、本当に唯一のかたちなのだろうか?
国家と“防衛”の結びつきはいつから?
近代国家の成立にともない、武力の組織化は国家の中心的な役割となった。
特に19世紀以降の徴兵制や常備軍の制度化によって、
「守ること」は国家の正当性そのものとされるようになった。
これは、マックス・ウェーバーが「国家とは、正当な暴力の独占者である」と定義した背景でもある。
国家が暴力を独占し、国民はその暴力に守られる──
このモデルは、秩序と防衛を国家に“預ける”仕組みを作った。
だが、この仕組みができる前、人びとはまったく守られていなかったのだろうか?
「国家がなければ無防備」は本当か?
国家という枠組みができる以前、あるいは国家による保護が届かない場所では、
人びとは地域や集団、慣習や信頼のネットワークによって自らを守ってきた。
- 村落共同体による相互警戒
- 自治都市における市民兵制度
- 先住民社会における“責任ある戦士”の存在
- 地域間の不文律による抑止と仲裁
それらはすべて、“国家”という上位構造がなくても成立していた別種の防衛のかたちだった。
にもかかわらず、現代では「国家なきところに秩序なし」「無政府=無防備」という発想が常識になっている。
これは一種の“想像の思考停止”と言っていいかもしれない。
「守られる」という発想の裏側
ここで重要なのは、「守られる」という言葉には、
同時に「自分では守れない」という前提が含まれていることだ。
つまり国家による国防とは、主権の代行と同時に、
市民の防衛能力・責任の剥奪でもある。
- 警察がいるから自分で守らなくていい
- 軍があるから考えなくていい
- 国家があるから“誰かが何とかしてくれる”
この安心感は強い。だが裏を返せば、
「自分たちで守る社会の構想を放棄した結果」でもある。

「国家がなければ守れない」は近代的な思い込み?
近代国家が「暴力の独占」を制度化したのは、せいぜいここ数百年の話。
それ以前、人びとは地域共同体・信頼・慣習などを基盤に、国家を介さずに秩序と安全を保っていた。
国防=国家の専売特許、という発想は、近代国家の正当性を裏付けるための後付けの常識にすぎない。
守る方法は、本当はもっと多様だったはずなのに。
武力の独占と国家の暴力装置
国家は、秩序を守る装置である。
だが同時に、国家は暴力を合法的に行使できる唯一の存在でもある。
この構図を、社会学者マックス・ウェーバーは明確に定義した。
「国家とは、正当な暴力の手段を独占する人間の共同体である」
この一文が意味するのは、国家だけが合法的に人を拘束し、罰し、殺す権限を持つという事実だ。
それは「暴力を使ってはいけない」という一般人の倫理と、「暴力を使う義務がある」国家の論理との間に、深い非対称性をつくり出す。
暴力の“正義”が国家に預けられる
国家の暴力は、ふだんは見えない。
しかし警察、軍隊、拘置所、刑務所、税務署──
すべてが「国家の命令を拒否したときの帰結」を背後に持っている。
私たちは、暴力をふるわれないように、
自分から法律に従い、税金を納め、命令に従う。
つまり国家の暴力は、「使わなくても効いている」状態をつくる。
それは、**恐怖ではなく“納得された強制”**のかたちで社会に浸透している。
暴力を“預ける”ことのリスク
ここで問題なのは、国家に暴力を独占させることが、
市民の“防衛能力”と“責任”を奪うことでもあるという点だ。
- 自分では争いを止めない。警察を呼ぶ。
- 自分では地域を守らない。自衛隊に任せる。
- 自分では考えない。国家の判断を信じる。
この委託構造の中で、人びとは「暴力を手放す代わりに秩序を得る」ことに慣れていく。
だが、その秩序が誰かを踏みにじっていたとき、
その暴力を誰が止めるのか?
国家が暴力を誤って使ったとき、
市民がそれを修正する手段を持たなければ、
暴力は“誤用されても止まらない力”へと変質する。
国家の暴力装置は「市民を守る」と限らない
国家の暴力は、常に「市民の安全のため」と説明される。
だが歴史を振り返れば、その暴力はしばしば国家に異を唱える市民に向けられてきた。
- クーデターを起こした軍は、「国を守るため」と言った
- 弾圧を行った警察は、「秩序維持のため」と言った
- 国家が戦争に向かうときも、「国民の生命と財産を守る」と言った
暴力の“使い方”を決めるのが国家である限り、
そこに「誰の安全か?」という視点が抜け落ちる危険がある。

国家だけが“正当な暴力”をふるえるのはなぜ?
社会学者マックス・ウェーバーは「国家とは正当な暴力の手段を独占する存在」と定義した。
つまり、拘束・逮捕・戦争など、一般人なら犯罪になる行為も、国家が行えば“合法”とされる。
この暴力の独占は、秩序のための手段であると同時に、市民の手から“守る力”を奪う構造でもある。
そしてその独占が“当然”とされることで、暴力の使い方を疑う視点が失われていく。
“武力なき防衛”は幻想か?
アナーキズムに対する批判の中で最も多いのが、「じゃあ、外敵に襲われたらどうするのか?」という問いだ。
国家を否定して秩序を求めることは、「無防備の理想主義」にすぎないのではないか?と。
たしかに、軍隊や警察という暴力の装置を否定すれば、
無秩序、内乱、侵略への脆弱性は避けがたく見える。
だが、「武力なき防衛」が幻想であると断じる前に、“防衛”とは何かを問い直す必要がある。
非暴力は立派だが万能ではない
ガンディーの非暴力運動や、キング牧師の公民権運動──
暴力を用いずに社会変革を実現した例はたしかにある。
しかしそれらは、暴力を行使する国家の“道徳”や“世界世論”に訴える前提があって成立していた。
つまり、「相手が暴力の限界を理解していること」が暗黙の条件だった。
だが、もし相手がそれを理解しない国家や武装勢力であればどうなるか?
- 「話し合おう」と言ったところで無視される
- 「無抵抗であること」が、ただの「無力」と見なされる
こうした現実が、非暴力の防衛には限界があることを示している。
暴力の否定ではなく、独占の否定へ
アナーキズムが目指すのは、必ずしも「完全な非暴力社会」ではない。
むしろ、暴力が特定の階級や国家にだけ正当化される構造を問題視している。
- 国家の暴力は「秩序維持」
- 民衆の暴力は「暴動」や「テロ」
このダブルスタンダードを是正することが、第一歩なのだ。
武力そのものを完全に排除するのではなく、
誰がどのような目的で、どのような責任をもって武力を扱うのかを問い直す。
そこに、「武力の非国家的管理」「共同体による自衛」という道筋が見えてくる。
武力を排除しなくても、“中央集権”は避けられるか?
ここで浮かび上がるもう一つの論点が、「武装=ヒエラルキー」の問題である。
軍事組織はその性質上、命令系統を必要とする。
つまり、上意下達の構造が発生し、権力が集中しやすくなる。
アナーキズム的な秩序と、武装組織が共存するには、
- 分散型の防衛
- 自治単位での防衛責任
- 任期制・交代制・合意制の武装管理
といった工夫が不可欠になる。
この発想は、「防衛の脱国家化=パラミリタリー化」ではなく、
“責任のある武装”と“非ヒエラルキー的な訓練”の可能性を示唆している。
理想は現実とぶつかる──構造的な欠陥をどう扱うか
こうした分散型・非ヒエラルキー型の防衛モデルには、
はっきり言って構造的な限界がある。
- 命令系統の欠如は、即応性の欠如を意味する。
- 合意制は、意見の対立が致命的な遅延を招く。
- 暫定的な指揮では、長期的な戦略遂行が難しい。
国家のような強制力がないということは、
**「守られたいと望む人びとが、その意志と責任で守りに参加する」**しかないということだ。
それは美しく聞こえるが、戦術的に見れば圧倒的に不利だ。
実際、正規軍と衝突すれば、装備、情報、統率の面で劣勢になるのは避けられない。
それでも「こうありたい」と思う人びとがいる
では、なぜそんな不利な立場をとる人びとがいるのか?
それは、彼らが「勝てる戦い」をしているのではなく、
「屈したくない現実」を生きているからだ。
支配に従わない。
命令されずに守る。
犠牲の意味を、自分で考える。
その生き方には、戦術的合理性はないかもしれない。
だがそこには、「武力とは誰のものか」という問いを投げかける力がある。
アナーキズムの防衛思想は、実用的ではないかもしれないが、思考を止めさせない。
それが最大の価値かもしれない。

アナーキズムって、勝つための戦術じゃないんだよね。
どこまでいっても、「どう生きたいか」の話なんだ。
勝てないのかもしれない。でも、従って負けるよりは、
不器用でも、自分で決めて動いた負けのほうが、ちょっとだけ納得できる。
ロジャヴァ──アナーキズム的自治と民兵の共存
アナーキズムは机上の理想ではない。
その思想を、戦争と国家のはざまで**“実装”しようとした場所**がある。
それが、シリア北部に存在するロジャヴァ(西クルディスタン)自治区だ。
ここでは、国家を持たず、中央政府とも敵対しながら、
アナーキズム的自治と、民兵による武装防衛が同時に存在している。
国家なき自治の中で、戦いは日常だった
ロジャヴァは、シリア内戦の混乱の中で事実上の独立自治を獲得した地域である。
指導理念の中心にあるのは、クルド系政治思想家アブドゥッラー・オジャランの提唱した**「民主的コンフェデラリズム」**。
この思想には以下のような特徴がある:
- 国家に頼らず、地域ごとの自己決定
- 上下関係ではなく、水平的な合議と協議
- 民族、宗教、ジェンダーを超えた包摂的な自治体構造
- そして、「自己防衛」を前提とした武装組織の存在
YPG/YPJ──アナーキズムと武装の両立は可能か?
ロジャヴァでは、以下のような民兵組織が自治とともに機能している:
- YPG(人民防衛隊)──主に男性で構成される住民防衛部隊
- YPJ(女性防衛隊)──女性による独立した武装組織
これらは正規の国家軍ではなく、**「市民による共同体防衛部隊」**という立場をとっている。
その運営にはいくつかのアナーキズム的要素がある:
- 指揮官は選出制であり、任期制
- 軍事訓練は全市民が受ける機会を持つ
- 武装の目的は国家の支配ではなく、共同体の防衛
ただし実態は、戦争という極限状況の中で、
理想を完全に貫くことは難しく、しばしば現実との妥協がある。
女性解放と防衛が結びつく社会
ロジャヴァで特に注目されるのが、YPJに代表される女性の武装参加である。
彼女たちは単に兵士ではなく、「パトリアルキー(家父長制)に対する防衛者」という立場をとる。
つまり、
- 敵はISISなどの外敵だけでなく、
- 家庭内の抑圧、伝統的な男権構造そのもの
という思想が貫かれており、防衛と解放が重なるのが特徴だ。
これは、国家軍による一方的な“女性の保護”とは根本的に異なり、
「支配されない主体として、自ら闘う女性像」を提示している。
理想の中にある現実、現実の中にある理想
もちろん、ロジャヴァも完璧なアナーキズム社会ではない。
- 政治的主導勢力(PYD)による意志決定の集中
- 経済面での外部依存(特に欧米の支援)
- 戦時下ゆえの情報統制・緊急対応的な統率
など、「非国家的」と言いながら国家的要素を帯びざるをえない側面もある。
それでも、ロジャヴァは問いを投げ続けている:
「国家を持たずに、人は武装し、秩序を作り、関係を守れるか?」
この問いを現場で引き受けながら、彼らは今も戦っている。

ロジャヴァとは?国家なき“自治と防衛”の実験場
ロジャヴァは、シリア北部にあるクルド人主体の事実上の自治区で、
「民主的コンフェデラリズム」という理念に基づき、国家に依存しない自治を展開している。
住民による合議制、女性の積極的参画、民兵による地域防衛など、アナーキズム的要素を現実に組み込んだ珍しい例。
理想と現実のせめぎ合いの中で、「国家を持たずに秩序と安全は成立するか?」という問いに挑み続けている。
私たちは何を“守る”べきか?
「国を守れ」と言われたとき、
私たちは何を思い浮かべるだろう?
国土か?制度か?国旗か?それとも、そこに暮らす人びとか?
その問いに即答できる人は、実は少ない。
そしてアナーキズムは、そこにこそ問いの本質があると言う。
国家を守ることと、人を守ることは同じか?
近代国家は、「国を守ること=国民を守ること」と等式で結んできた。
戦争も徴兵も治安維持も、すべて「あなたたちのために」と説明される。
だが、ロジャヴァのように国家なき秩序を構想する立場から見れば、
「国を守る」はときに、「国家という枠組みを優先する」ことであり、
「市民個人の意志や関係が後回しにされる」ことでもある。
つまり、守られる側が**何を守ってほしいかではなく、国家が“何を守ると決めたか”**が優先されるのだ。
“誰が決めた”防衛か?
防衛には2種類ある。
- 誰かが決めた“防衛されるべき対象”を守る防衛
- 自分たちで“何を守りたいか”を決める防衛
アナーキズムは後者を選ぶ。
たとえそれが非効率で、統一感がなく、脆く見えたとしても、
守る対象と守る方法を“他人に決めさせない”ことこそが、自由の本質だと考える。
だからアナーキズムは、武力を否定するのではなく、
支配のための武力を拒否し、関係性を守るための武装を模索する。
“守ること”は、恐怖ではなく関係から始められるか?
私たちは、恐怖によって防衛を語られることに慣れている。
- 「敵が攻めてくるから防衛力を」
- 「テロの脅威があるから監視を」
- 「混乱を防ぐために秩序維持を」
だが本来、“守る”とはもっと能動的な行為のはずだ。
- 守ることで、関係を維持する
- 守ることで、相手に信頼を返す
- 守ることで、「支配されない安全」を手に入れる
このような関係ベースの防衛論こそ、アナーキズムが問いかけている視座である。
最後に──私たちは、選べる──
国家の防衛力に頼ることもできる。
だがそれは、守る対象も方法も“委任する”選択でもある。
もう一つの道は、自分たちで考え、手間をかけ、責任を引き受ける防衛だ。
それは不器用で、頼りなく、理解されにくい。
だが、それでも私たちはこう問えるようになる
私たちは、本当に「国家」を守りたいのか?
それとも、「誰かと支え合える関係」を守りたいのか?
アナーキズムとは、選びなおす自由のことである。

「国を守る」ってよく聞くけど、
守ったあとの“中身”まで考えてる人、どれくらいいるんだろうね。
ボクはね──大事なのは、誰かに命じられずに「これを守りたい」って思えるものがあることなんだと思うよ。
シリーズ:アナーキーという秩序
- 「国がなければ無秩序」は嘘?グレーバーが見た“もうひとつの秩序”
- 交換が社会をつくるモースの『贈与論』が照らす“与えあう秩序”の原型
- 国家は誰のものか?人格化された国家から装置としての国家へ
- 今読んだ記事→ 「無政府状態=無防備」なのか?──アナーキズムと“自衛する社会”の可能性

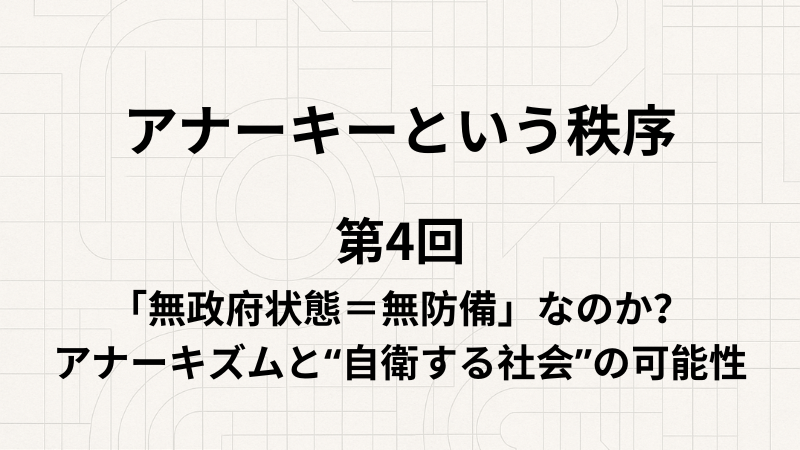
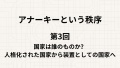

コメント