「日本人の税金は日本人のために使うべきだ」
「アメリカはアメリカ人の雇用を守れ」
一見もっともらしく聞こえるこのスローガンは、トランプの「アメリカ・ファースト」や日本で広がる「日本人ファースト」に象徴されるように、近年の内向きな社会の空気をよく表している。
自国民を優先する
それは感情的には納得しやすく、政治的にも支持を集めやすい。
だが、避けられないグローバル化社会において「自国第一主義」はほんとうに国民の利益を守る手段なのだろうか?
本稿では、「日本人ファースト」と「アメリカ・ファースト」というふたつのスローガンを比較しながら、その合理性と限界、そして長期的コストについて考えてみたい。
「〇〇ファースト」の誘惑──誰にとって心地いいか?
「〇〇ファースト」というスローガンには、強い吸引力がある。トランプの「アメリカ・ファースト」も、日本でよく耳にする「日本人ファースト」も、要するに「私たちを優先せよ」というメッセージだ。そしてこの“私たち”という言葉の輪郭は、国籍や民族、文化、あるいは言語といった要素でゆるやかに定義されている。
この種のスローガンが支持されるのは、単に排外的な意図からではない。もっと根源的な動機として、人々が社会の変化についていけず、不安や疎外感を抱えているとき、「自分たちが軽視されている」という感覚を補う役割を果たすからだ。
グローバル化が進み、移民や外国人労働者の存在感が増すなかで、「国民の税金が外国人に使われている」「自国の雇用が他国に奪われている」といった言説は、ごく自然な“危機感”として受け取られる。
政治家がこの空気を利用するのはたやすい。「あなたたちの味方ですよ」と訴えかけるには、「〇〇ファースト」はあまりに便利な言葉だからだ。
しかもそのメッセージは、善悪や複雑な制度設計を持ち出さなくても、瞬時に伝わる。誰かを直接攻撃する必要もなく、“敵”をぼんやりと指差すだけで、自分の側に立っているという印象を与えられる。
だが、そこで立ち止まって問うべきは、それが本当に「自分たち」の利益にかなっているのかということだ。「優先する」という行為には必ず何かを「後回しにする」誰かがいて、社会のつながり全体に見えない歪みが生まれる。
それは、見かけ上の“安心”と引き換えに、じわじわと自らの生活の基盤を削っているかもしれない。
短期的には得をした気になる──“国内向けパフォーマンス”の力
「外国人への支出を減らしました」──この一言は、数字としても感情としても、わかりやすい成果として響く。
生活保護の予算から何億円、子育て給付から何千万円、医療補助や学校給食の無償化から外国人分を除外。帳簿上はたしかに支出が減る。その瞬間だけ見れば、“税金のムダ”がなくなったように見える。
そして、それが拍手されるのは、“実感”に訴えているからだ。「ああ、ちゃんと私たちのために使われているんだ」と思わせる効果がある。実際には、削った額よりも桁違いの予算が別の用途に流れていても、「見える削減」が心理的インパクトを持つ。
このような施策は、実態よりもパフォーマンスとしての意味が大きい。選挙対策、支持率回復、危機の代替的な矛先……いわば“感情のコストカット”だ。
そしてそれがうまく機能するのは、対象が「外国人」であることが多い。目の前にいない、声を上げにくい、共感しづらい。だから反発も少なく、「政治的においしい削減対象」になりやすい。
だが、そうした政策の効果は、たいてい数字よりも短命だ。社会保障の持続性は改善されず、労働力不足は放置され、地域の人口減少にも歯止めがかからない。
一方で、外国人側には「歓迎されていない」という無言のメッセージが伝わり、長期的な信頼関係や人材の定着は失われる。
「自国民のため」として支持された政策が、じつは自国民の未来を削っている──そんな構図は、表面的な“得”の裏に潜んでいる。
しかし制度はつながっている──切り捨ての代償
社会制度というのは、単独で成立しているように見えて、実は複雑につながり合っている。生活保護、医療、教育、労働、年金。これらは「使う人」と「支える人」が入れ替わりながら全体として均衡を保っているシステムだ。
ところが、「日本人ファースト」や「外国人排除」の発想に立つと、制度の一部を切り離すことで“節約”できると考えてしまいがちだ。
たとえば、外国人への生活保護を止めれば財政が軽くなる、外国人への出産一時金を廃止すれば無駄が減る。数字の上ではそのとおりかもしれない。
だが、その一方で、彼らが支えている制度の側面が無視されている。
日本で働く外国人は、健康保険料も年金も消費税も払っている。雇用主を通じて厚生年金にも加入し、失業保険の財源にも貢献している。
外国人を排除すれば、支出は減るかもしれないが、収入も確実に減る。
それだけではない。介護現場、建設現場、物流、農業、飲食……
いまや多くの業種が外国人の労働力で“かろうじて”回っている。
外国人がいなくなれば、単に福祉費が浮くどころか、サービスそのものが維持できなくなる。
行政サービスも、経済活動も、税収すらも連鎖的に弱体化する。
つまり、制度というのは「誰にいくら払うか」ではなく、「誰がどう支えているか」まで見ないと、全体のバランスはつかめない。
一部だけを切り取って「ムダを省いた」と言っても、その反動は別の場所に現れる。目先の“節約”が、じつはシステム全体の“損失”につながる。それが、切り捨ての代償である。
排除にはコストがかかる──“差別”は無料ではない
「外国人に税金を使うな」と言うのは簡単だ。だが、実際にそれを制度として実行しようとすると、想像以上に手間とコストがかかる。
まず、対象の選別。生活保護や補助金を支給する際に、「この人が日本人かどうか」「何世か」「滞在資格は何か」「永住か、一時的か」「扶養家族の範囲はどうか」など、国籍や滞在条件に基づく線引きの確認作業が必要になる。しかも、それは一度だけではない。継続的に管理・更新が求められる。
さらに問題なのは、こうした線引きが現場に混乱をもたらすことだ。
役所、病院、学校、職場――そこにいるのは制度の“対象者”ではなく、生身の人間である。
「あなたは外国人だからこのサービスは使えません」と、窓口で伝える責任を背負うのは、最前線の職員たちだ。
現場にとっては、明確なルールがあるほどに、判断の余地がなく、融通がきかない。
加えて、排除された人が消えてなくなるわけではない。制度にアクセスできない人々は、病院に行かずに症状を悪化させる。
住民票を持たずに働き、非正規・非合法な労働に従事する。子どもは教育を受けず、将来の社会参加が断たれる。
そうした“影の社会”が広がれば、治安・衛生・人権問題として、結局は別の形で社会コストが跳ね返ってくる。
つまり、「排除」は無料ではない。むしろ、排除するためにコストを払い、さらに排除した結果に対処するためにコストを払うという、二重の出費が生じる。
制度をシンプルに保ち、包括的に運用するほうが、トータルではむしろ効率的な場合がある。
「自国民を守るため」という名目で始まった選別が、やがて制度そのものを蝕む。
差別や排除の制度設計には、見えにくい費用と見えにくいリスクが確実に存在するのだ。
「差別は高くつく」──ジム・クロウ法の経済的教訓
アメリカの南部で、かつて「ジム・クロウ法」と呼ばれる制度があった。
白人と有色人種を分ける人種隔離法で、学校、病院、レストラン、バスの座席、果てはトイレや水飲み場に至るまで、あらゆる公共サービスが“二重化”された。
白人専用と非白人専用──その区別を守るために、政府や自治体はすべてを2セット用意し、2つの運用コストを払い続けた。
しかも隔離の維持には、監視、取り締まり、訴訟対応なども含めて莫大な管理コストがかかった。
結局のところ、これは倫理の問題であると同時に、制度としても非合理な「高コスト設計」だった。
差別や排除は、単なる感情の発露では済まず、社会全体にとって“割に合わない構造”を生むということだ。
アメリカと日本、似て非なる“余裕”の違い
「アメリカ・ファースト」と「日本人ファースト」は、スローガンとしてはよく似ている。どちらも“自国民優先”を掲げ、グローバル化や多文化共生に対する不満を背景に支持を集めてきた。
だが、このふたつを同列に扱うと見誤る。アメリカと日本では、抱えている前提条件がまったく異なる。
アメリカは世界最大の経済規模をもち、軍事、外交、通貨、文化すべてにおいてグローバルな影響力を持つ国だ。多少の強引さや排外的な姿勢をとったとしても、その衝撃を自国内である程度吸収する“余裕”がある。
たとえばトランプ政権が貿易摩擦を起こした際も、アメリカ企業の規模とドルの強さが、それを支える一定のクッションになった。
一方、日本はどうか。
経済は外需依存が強く、人口は急速に減少し、労働力不足は構造的な課題になっている。少子高齢化によって社会保障の支え手は減り続け、地方は衰退を避けられない状況にある。
つまり、日本は「内向き」に転じれば転じるほど、自らの首を絞める構造になっている。
もうひとつ重要なのは、アメリカはそもそも「移民国家」であるという点だ。移民前提の制度設計がされており、排除のコストや反発はあるにせよ、それでも制度が吸収するだけの土台がある。
対して日本は、「移民政策をしていない」という建前を保ちつつ、実質的には外国人労働者に多くの領域を支えさせてきた。
そのため、排除にも包摂にも本格的に対応できる制度が整っておらず、中途半端なまま社会の負荷だけが蓄積している。
つまり、同じ「ファースト」でも、アメリカは“踏ん張れる”が、日本は“もたない”可能性が高い。
この違いを無視して、スローガンだけを真似れば、見えるのは強さでも誇りでもなく、自滅への道筋である。
「ブロック経済」ができる国、できない国
1929年の世界恐慌は、あらゆる国に深刻な打撃を与えた。だが、その後の回復策には、国家ごとの“余裕の違い”が如実に表れた。
イギリスやフランスは、自らの植民地を囲い込むブロック経済圏を構築し、関税と輸入統制で自国の経済を守った。
アメリカも例外ではなく、広大な国内市場と中南米との関係を活かして、事実上のブロック経済を作り上げた。
一方、日本やドイツは、そうした「囲い込む外縁」を持たなかった。資源も市場も外に求めるしかなく、国際社会からの孤立は経済的な死を意味した。
だからこそ日本は満州へ、ドイツは東欧へと“自前の経済圏”を武力で確保しに行く──という、暴走ともいえる道を選んでいく。
同じ「内向き」でも、もともと囲いを持つ国と、そうでない国とでは選べる戦略が違う。
これは現代においても、「アメリカ・ファースト」が一定の独立性を保てた理由であり、逆に日本が「日本人ファースト」で同じことをすれば、外との接続が途絶えて成り立たなくなる可能性が高いことを示している。
“自分たちのため”なら、もっと長期で考えるべきだ
「自国民を守れ」というスローガンは、誰にとっても耳ざわりがいい。
「あなたのために」「私たちの税金を私たちに」という語り口は、敵を生まずに安心だけを与えてくれる。
だが、もし本当に「自分たちのため」を考えるなら、それは短期的な感情の満足ではなく、長期的な制度の持続性や社会全体の安定に目を向けるべきではないか。
たとえば、目の前にある福祉の支出を削って「スッキリ」することと、将来の労働力や税収を維持すること。
どちらが“得”かは、数字を少し先まで見れば明らかだ。外国人排除が仮に一時的な財政の軽減につながっても、それによって制度を支える側が減り、コストを共有できる人がいなくなるなら、本末転倒である。
あるいは、社会の分断や不信感が進むことで、サービス提供の現場が疲弊し、外国人だけでなく**“日本人ですら制度にアクセスしづらくなる”社会**になっていく。
それは結局、守るべき“私たち”の暮らしを脅かす。
制度というのは、自分が元気で豊かなときだけでなく、弱ったときにも支えてくれるネットであるべきだ。
誰かを締め出す構造は、回り回って、自分が落ちたときに助けが来ない構造にもなりうる。
「〇〇ファースト」という言葉は、たしかにわかりやすくて気持ちがいい。
だが、その言葉が真に“自国民のため”になるかどうかは、むしろその先を見通す力にかかっている。
本当に“自分たちのため”を思うなら──
今こそ必要なのは、「誰を切り捨てるか」ではなく、「どう一緒に支えあうか」の制度設計なのではないか。


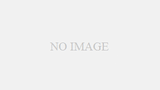

コメント