最近、埼玉に住むクルド人コミュニティに対する報道が目立っている。「外国人が増えて治安が悪くなった」とする地域住民の声が取り上げられ、SNS上でも「クルド人は危ない」「不良外国人は排除」といった言説が散見されるようになった。
だが、これらの声は本当に「事実」を反映しているのだろうか。私はそうは思わない。むしろ、こうした言説の多くは、クルド人への漠然とした「違和感」や「不安感」といった感覚の表出に過ぎず、実態とは大きく乖離している。
私自身の経験にもそれを裏づけるものがある。ヨーロッパのとある都市を訪れた際、ユダヤ教の超正統派が多く住む地域に足を踏み入れたとき、どこか緊張感のようなものを覚えた。彼らが何かをしてきたわけではない。ただ、服装も文化もまわりとはあまりに違って見え「なんとなく怖い」と感じてしまっただけだった。
プノンペン郊外のムスリム地区を歩いたときも同様だった。特に危険な出来事があったわけではないが、プノンペンの市街地とは全く異なる文化の空間に身を置くことで、なんとなく不安が先行する。
冷静に考えればそれは単に「慣れに対する戸惑い」に過ぎなかったと理解できる。だがその瞬間は漠然としたなんとなく怖いという感想を持ってしまった。
この感覚こそが問題であり日本でも同じような構造があると思う。
またこのようなこともあった。
以前、外国人が多い地域に住んでいたことがあった。あるとき自転車を盗まれ、交番に届けに行くと警察官はこう言った。
「この辺は外国人が多いからね」
その言葉に、私は一瞬、耳を疑った。自転車の盗難について、犯人も分かっていない段階で、まるで外国人が犯人のように決めつけて話していたからだ。
本人に差別的な意図は一切なくそれがあまりにも当然のように語られたことにも、驚きがあった。後日幾人かの知人に話してみても、特に問題視する反応はなく、むしろ「何が問題なの?」という反応ばかりだった。
この違和感に気づかない感覚こそが、差別や偏見を日常に溶け込ませる回路になっているように思える。
では、こうした発言を別の属性に置き換えたらどうだろうか。「この辺は中卒が多いからね」あるいは「非正規労働者が多いからね」と言われたら、多くの人は眉をひそめるはずだ。中卒でも真面目に働いている人はいる。むしろほとんどの人はそうだ。
たとえ統計的に犯罪率が高い傾向があったとしても、属性でラベリングするような言い方は不適切だ──そう考える人は少なくない。(少なくとも表面的には)
ところが、「外国人」に関しては、それがなぜか許されている。
心理学的には人間は、自分が属する集団(内集団)には多様性を認めるが、外の集団(外集団)に対しては「みんな同じだ」と見なす傾向がある。
これは内集団バイアスおよび外集団同質性バイアスと呼ばれる。
つまり、「日本人の中にも悪い人はいる」という前提は守られる一方で、「外国人は怖い」「外国人が多いとトラブルが起きる」というステレオタイプは、個別の事例ではなく属性そのものに原因があるかのように語られてしまう。
これは単なる感情や感覚が差別的な言説の入り口となり無批判に広まっていく。
それでもなお、「治安が悪くなった」という声が、事実として社会に定着してしまうのはなぜか。その理由のひとつは、私たちが「治安の悪化」を数値ではなく感覚で判断しているからだ。
見慣れない言葉、習慣、外見を持つ人々が集団がいた──この違和感が「なんとなく怖い」「治安が悪くなった気がする」という印象につながる。
そして、その結果、実態とは乖離した「クルド人が来てから治安の悪化を感じる」と答える人の割合の増加につながったのではないかと考える。
だが、それは本当に悪化なのだろうか。
ただ単に、「自分とは違う文化を持つ人たちが可視化されるようになった」というだけではないのか。
実際、外国人による犯罪の増加が統計に顕著に現れているわけではない。それにもかかわらず「外国人が治安を悪化させている」という印象が強まる背景には、制度としての差別というより、むしろ無意識に共有された偏見の常態化がある。
私は、「外国人が怖い」「見た目が違うと不安になる」という感覚そのものを否定したいわけではない。それは人間として自然な反応でもある。
問題なのは、その感覚をそのまま「治安の悪化」や「排除の正当化」にまで持ち込んでしまう構造だ。それは社会の中に偏見を制度として埋め込んでいく行為に等しい。
「高校を中退しても真面目に働いている人はいる」という当たり前の言葉が通じるなら、「外国人でも真面目に働いている人はいる」もまた同じように受け止められるべきではないだろうか。
属性で人を語る言葉は、どんな文脈であっても、常に疑いの目を向けられるべきだ。
なぜならそこには、誰かの努力や存在を見えなくしてしまう構造が潜んでいるからである。



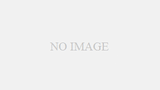
コメント